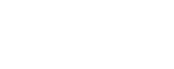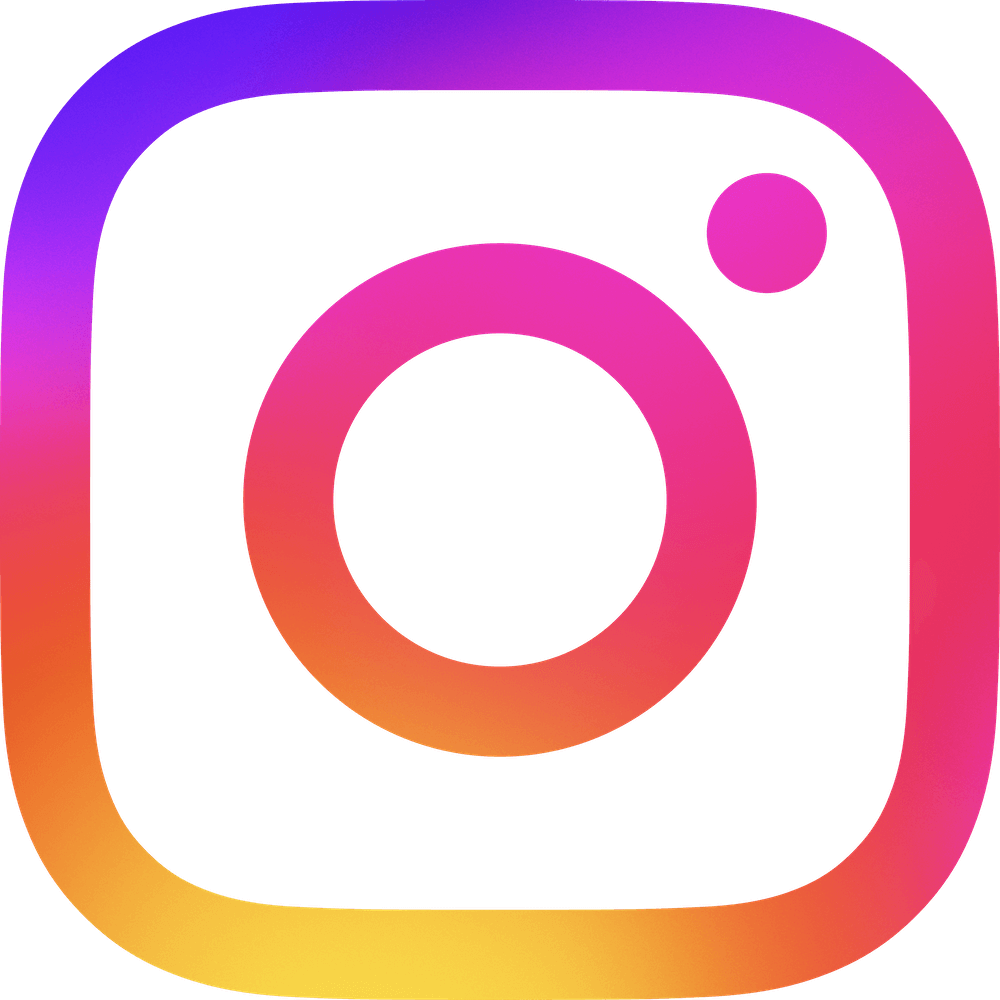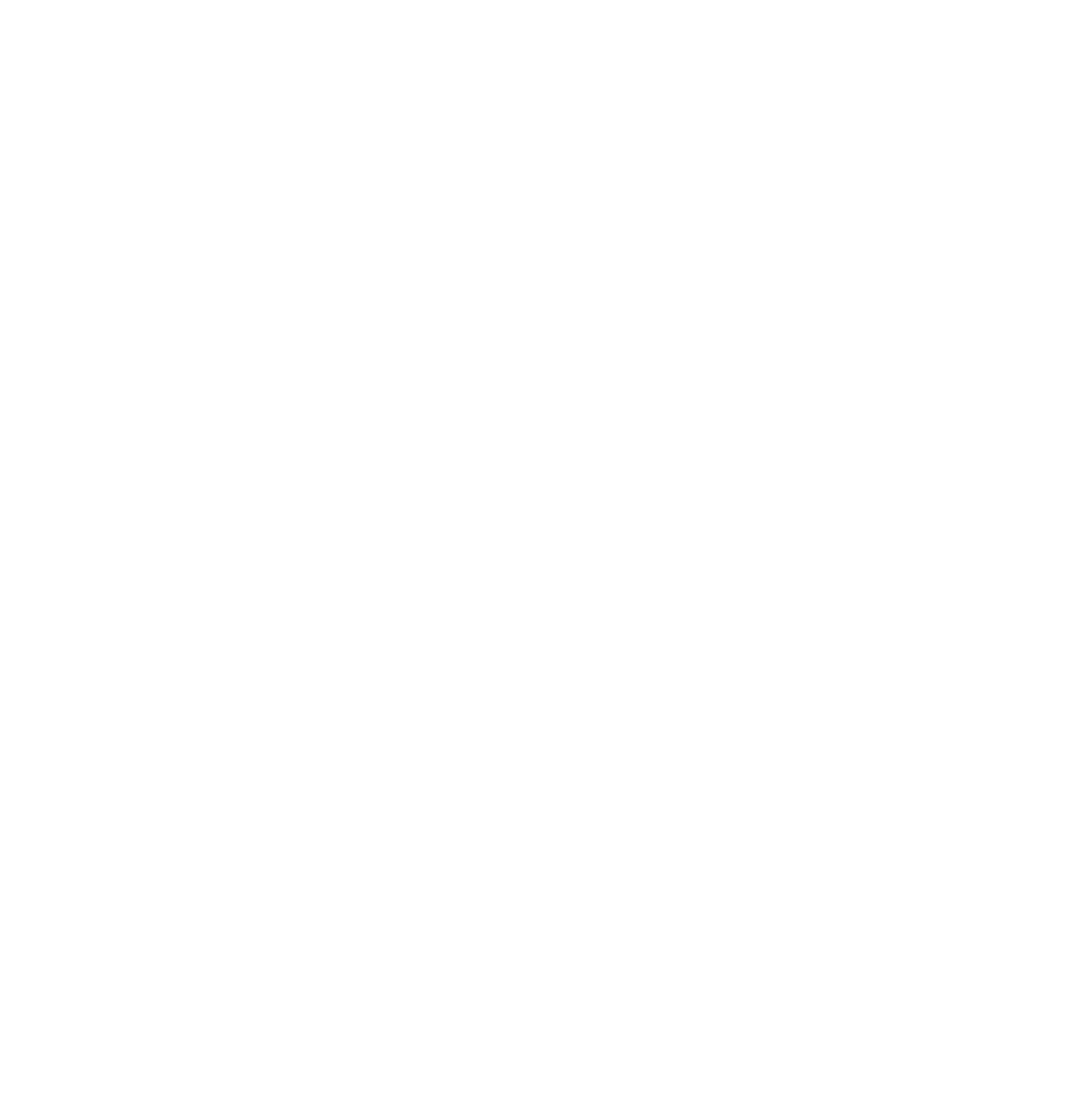伝統工芸と対等に向かい合い 職人と共に挑む日本の「近未来」
人々を驚かせる作品を次々と生み出すプロダクトプロデューサーの丸若裕俊さん。
彼のものづくりの原点を聞くと、そこには「人」とのふれあいがあった。

元々はストリート系のアートワークを手がけていた。

チタン製のタンブラー『竹』と、印傳を施した名刺入れ&キーホルダー。
2011年6月、金沢21世紀美術館に所蔵されることとなった丸若屋と上出長右衛門窯が製作した『髑髏のお菓子壷 花詰』。誰も見たことがないその斬新なプロダクトに、多くの人は「こうきたか!」と度肝を抜かれ、驚きとともに胸の奥で何かワクワクとした気持ちが弾けたのではないか。
そんな丸若裕俊さんのものづくりのテーマは “近未来” だと言う。現在でも過去でもない、ほんのちょっと先のものだ。
「僕のものづくりは、大昔に殿様がおもしろいものが見たいと言って、家来たちが血眼になってとんでもないものを作ってしまう感覚に近いかもしれません。使う人や手にとる人の仕事が、もっとクリエイティブになったり、アイデアソースになったり。人の感性を刺激するようなものを作りたいですね」
プロダクトを手にした人が何を思うのか。丸若さんのプロダクトは、その使い手の気持ちや考え、時に人生観までも動かしてしまう、言わば “起爆剤” のような役割を担うのかもしれない。
そんな丸若さんのものづくりは、決して固定概念に囚われることはない。昔から存在している伝統的なものも、新鮮な眼で見て、触れているからこそ、斬新な切り口が生まれるのだ。
「遠近感がなく多角視点で描かれた日本の大和絵のように、物事を多角的に見るようにしています。本当にかっこいいのか? 本当はダサイんじゃないか? って(笑)」
見慣れたものも、一度まっさらなところに置いてみる。そして、上から下から、様々な角度で見たり、時に逆さにしたり。常に新しい眼で見ることが、丸若さんのものづくりには不可欠なのだ。
元々ストリートカルチャーを主流に、イメージアートなどを手掛けていた丸若さん。今のものづくりも、ストリートの延長だと言う。
「正直、伝統工芸をどうにかしようとは思っていないんです。むしろ、ストリートでやってきた人間が、伝統工芸によって救われたんですよ。今の時代を、”技” のみで一点突破する、そんな職人としっくりくるのは、ストリートな感覚なのかもしれません。ジャンルは全く異なっていても、ものづくりのベクトルの方向の合う職人を組み合わせると、スペシャルチームができるんです」
2010年に発表された「上出長右衛門窯×ハイメ・アジョン produced by 丸若屋」も、そんな風に出会いが形となった事例だ。
「結局は、人」
丸若さんは、そうも語る。何を作っているのかを知るより、その人がどんな心意気で何を大切にしている職人/アーティストなのか。ひとつひとつの作品は、その内面でつながった結果なのだ。
伝統工芸の職人とタッグを組んだ丸若さんの作品の中で、なめした鹿革に染色を施し、漆で模様を描いた印傳のiPhoneカバー『otsuriki』は、ミラノサローネでも、Made in Japanアイテムとして一流デザイナーの間で話題になった。
「ミラノサローネの時は、現地の人の反応がおもしろかったですね。かっこいいかどうか、それだけで反応してくるんです。漆や素材のことを説明しても、全く聞いてない(笑)でも、それでいいんです。要は、イケてるのかどうか。それは、僕の一番の指針です。かっこいいモノに出会うと、かっこいいモノを作ろうとする故のピュアなバカさを感じて嬉しくなるんです。負けてられない!もっとバカになろう!と思うんですね」
丸若屋のプロダクトをきっかけに、もっとものづくりにバカになれる人が出てきたらいい。それは、丸若さんがものづくりをしながら、次世代のクリエイターに願うことだ。イケてるか否か。丸若さんのシンプルな二択は、振り切るところまで振り切ったロックな作風に全て表れているような気がする。
最後に「丸若さんにとってものづくりとは何か?」と問うと、こんな答えが返ってきた。
「ものづくりは、プレゼンテーション。自分のプレゼンテーションでもあり、日本のプレゼンテーションでもあります。日本を背負っているという感覚ではないけれど、日本人であるという自覚はどうしようもないんです」
幼少時代を横浜ですごし、様々な国の人と触れあう機会が多かったことで、『日本人であること』を常に意識していたという丸若さん。丸若屋というフィルターを通して見ることができる近未来の日本は、楽しさと刺激と粋の精神が溢れ、何でもできそうな無限大の可能性に満ちている。
丸若屋