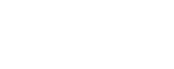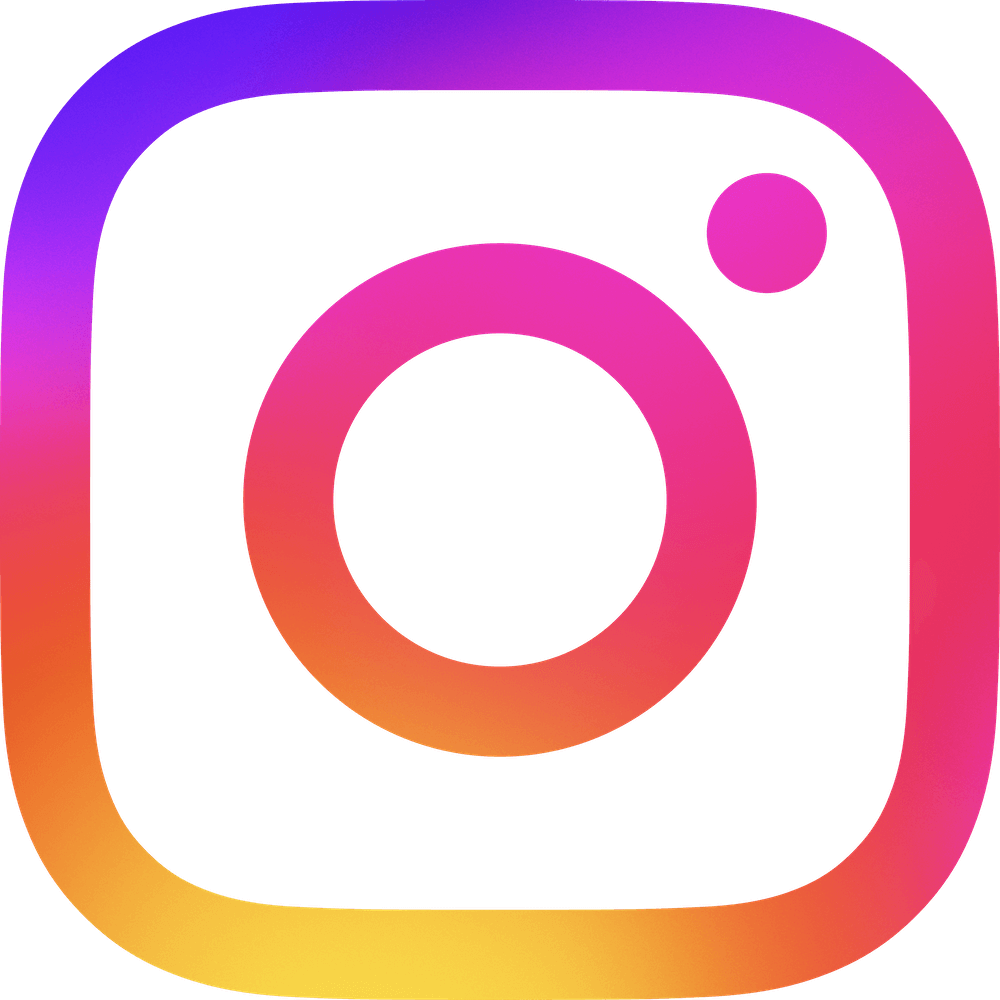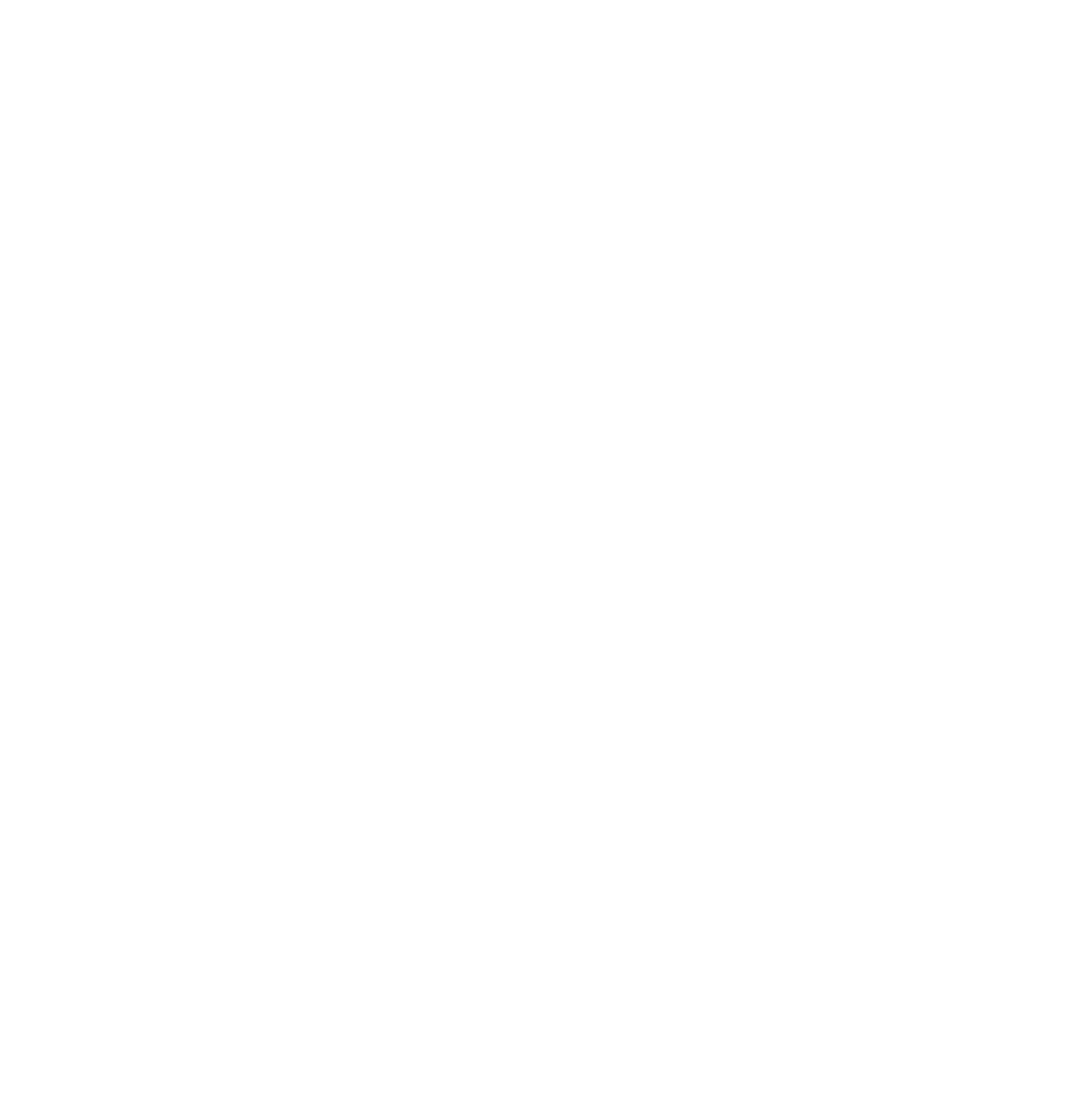余計なことはしない 自然体のジャム作り
肌身で感じた農村の実態
都会と果物を結びつけるために生まれた瓶詰めの店

「あるいはその他」のその他。自然栽培の野菜を使ったポトフは丹羽さんお気に入りメニューで900円。スモークオリーブオイルをかけて。

ジャムはもちろん、オーガニックコーラやゴマ油、オリーヴの瓶詰めなど、あらゆる「bin」ものが買えるショップでもある。

トンネルをひとつすぎれば芦屋市。いわゆるセレブ系マダム雑誌の撮影などでもこの地がロケーションとして使われることが多い。

丹羽さんがジャム作り、料理作りに使っているという和包丁。右の菜切包丁を使いマーマレード用にオレンジをスライスするという。
丹羽真矢さんが生まれ育った西宮・苦楽園の地にジャムの店を開くまでには紆余曲折があった。古いものをあまり大切にせず、お高くとまっているように感じていた地元が好きではなかった彼は、19歳の時にこの街を出た。それから14年間、東京でレストランやカフェでサービスの仕事に就いていた。転機が訪れたのは33歳のとき。友人から高知での仕事に誘われた。これまで経験したことのない田舎。そして、経験したことのない刃物屋という仕事だった。
住んでみると、都会にいるとわからないさまざまなことが見えてきた。林業も農業も漁業もさかんな高知では生活のすべてで刃物が密接に結びついていた。いろんな人たちの刃物を研いだ。次第に人々との関わりが濃密になり、野菜や果物をわけてもらうようになった。話を聞けば、採れ過ぎたため市場に回せないそれらは廃棄されるものだという。せっかく作った作物が誰の口にも入ることなく捨てられていく。これは、おそらく日本全国の農家で同じことが起きているのではないだろうかと考えた丹羽さんは、捨ててしまうくらいなら加工しようと考えた。できるだけ、余計なことをせずに。それがジャムという形に落ち着いた。
苦楽園という街は、関西でも屈指の高級住宅街のひとつに数えられ、建物はしばしば近代的なものに建て替えられていく。しかし、丹羽さんがたまたま見つけたのは、鉄骨造りの築40年の元クリーニング店。古いもの好きと意識したことはないけれど、見て惹かれるものに古いものが多いという彼は、この建物を壊してはならないと半ば自らの義務であるかのようにこの店を借りた。特に開業資金もあったわけではない。天井と壁と床は自分で張った。電気工事は地元の友人がやってくれた。家具も友人たちからもらった。店のロゴは通りかかったおじさんが作ってくれた。あとから聞けば、有名なデザイナーだったが……。外に掲げられていたクリーニング店のサインもそのままにした。
余計なことはしない、そして捨てない。それは信念というものより、もっとナチュラルな丹羽さんの姿勢だ。瓶詰めの店にしたのも、捨てずに回収できるから。成分表示のシールは貼るが、ラベルは張らない。回収時に返金していた20円は、今は被災地への寄付にしている。ジャムの原料は果物の場合は粗糖を加えるだけ。野菜のジャムならさらにレモン果汁を加えるだけだ。瓶詰めの店だから「bin」がいいのではないかという友人の言葉を店名にした。「ジャムと珈琲、あるいはその他」というのは、「ジャム屋でカフェです。他にも売っています」という意味なのだが、「カフェ」という言葉をいまさら使いたくなかった。
果物や野菜などの素材は、できれば自然農法のもの、そうでなければ有機農法のものを使っているが、あくまでも美味しいと感じているから。きっかけは店を開く直前の2010年8月、自然農法で作った野菜を店の前で売りたいという人の紹介を受けたことだった。旨さの違いに衝撃を受けた。美味しい素材を求めていると、柑橘なら愛媛・伊予市の福岡自然農園、トマトやルバーブなら長野のシーゲルファームと、情報が集まり、それらを使うようになった。高知界隈でしか食べられていない美粧柑などの珍しい果物にも出合った。
余計なことをせず、ものを大切にし、自然体であること。そうしていると「bin」という店が生まれた。これからも果物と苦楽園という街を結びつける存在でありたい、と丹羽さんは語った。