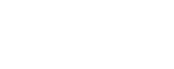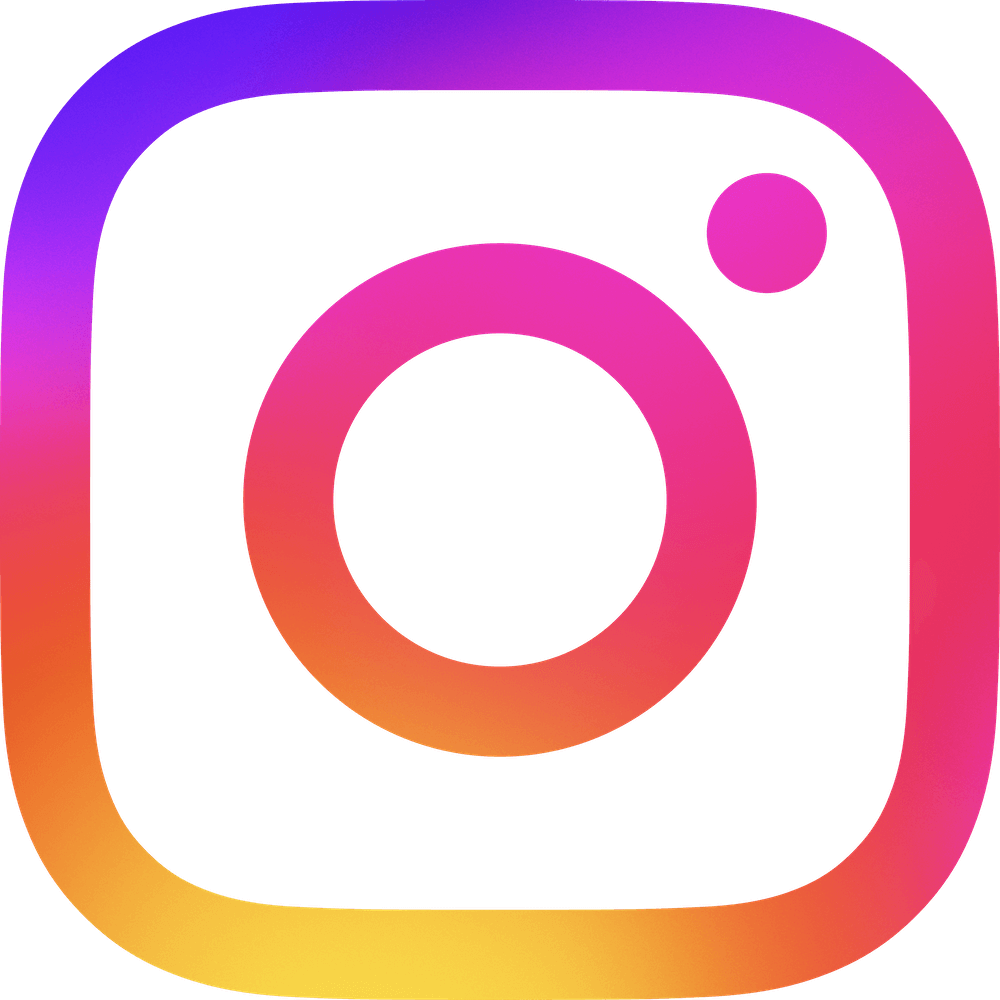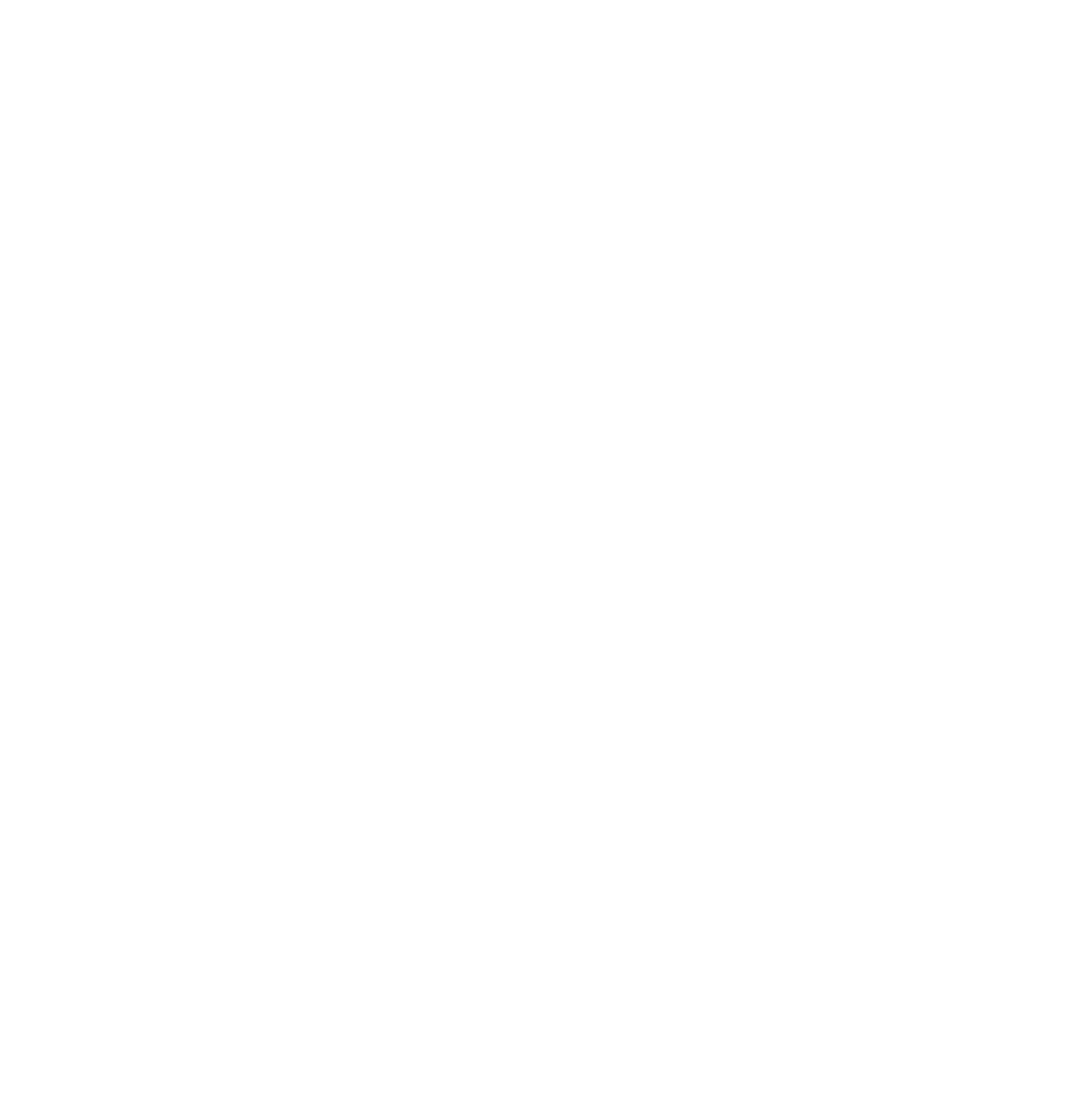My Jeep®,My Life. ボクとJeep®の暮らしかた。DJ / プロデューサー・田中知之(FPM)
「原点」、「スタンダード」という言葉をキーワードに、多彩なゲストを迎えてそれぞれのストーリーを紡ぐ連載企画「My Jeep®,My Life.」。今回はDJ / 音楽家として活躍するFPMこと田中知之さんが登場。昨年秋にデビューした「コンパス(COMPASS)」を運転しながら、自身のルーツである京都の音楽シーン、そして、現在の音楽に対するアティチュードについて語ってもらいました。


80年代、京都の音楽シーンから得たもの。
90年代よりDJ兼プロデューサーとして活躍するFPM田中知之さん。ダンスミュージックを軸とした楽曲は、国内だけに留まらず、海外でも広く認知され、現在も世界をまたにかける活動を行なっている。そんな田中さんがデビューしたてのニューモデル「コンパス」に乗り、音楽以外にこよなく愛するヴィンテージ古着を掘りに横浜へと向かった。車中では、田中さんの音楽のルーツに関する話題からスタートする。
「ぼくの音楽の原体験は中学生のとき。友達とバンドを組もう! ということになって、ベースを買ったのがはじまりです。それがたしか1980年くらい。当時、日本の歌謡曲やニューミュージックの勢いがすごかったし、一方でYMOやTHE PLASTICSといったコアなバンドもいて、音楽業界がすごく華々しい時代でした。はじめはヘビメタのコピーバンドとかやっていて、高校生になるとオリジナルのニューウェーブバンドに進化していきましたね」
テレビの地上波ではMTVの番組が普通にオンエアされ、アメリカのヒットソングの情報も自然とキャッチしていたという田中さん。テレビやラジオから流れてくるメジャーな洋楽が田中さんの心を刺激したのと同時に、京都のアンダーグラウンドな音楽シーンからの影響も計り知れないという。
「高校生くらいから、ドロドロのファンクだったりフリージャズを聴くようになりました。いま考えたら相当ませた高校生ですよね(笑)。京都には本当に変な先輩たちがたくさんいて、ノイズやハードコア、それにニューウェーブのバンドもたくさんあって、いい意味でゴチャゴチャしてて(笑)。スカのリバイバルも東京より全然早かった。THE SPECIALSに代表されるようなイギリスの2トーンスカのリバイバルが83年くらいには京都に完全に降りてきていましたし。音楽に関しては本当に豊かで、いろんなものを吸収できましたね」
具体的にどんなものを京都の音楽シーンから得たのか? そんな質問に、田中さんはこう答えてくれた。
「音楽として、どういったものがかっこいいのか? そういうものをジャッジする価値観のようなものが生まれました。当時は音楽に地域性のようなものがあったんです。例えば名古屋はパンクやハードコアが進んでいたし、福岡ではいわゆるロック・ミュージックが盛んだった。そんな中、京都の音楽といえばやっぱりニューウェーブでした。東京に対する憧れのようなものもあるんだけど、一方では『俺たちは京都の音楽をやっている』という自負もありましたね」


高校生のときに知ったレコードを集める快感。
大学に入っても継続してバンド活動に熱を上げ続ける。「学校には行かずに、バンドばっかりやってました。完全にプロ志向だったんですよね」と田中さんは笑いながら話す。
「当時、ぼくは『マハラジャ』というディスコで皿洗いのバイトをしていたんです。バンドばかりやっていたぼくがDJという存在を知ったのはそのとき。ブースに立って、ヘッドホンを耳に当てて『あの人たちは何やってるんだろう?』って興味をもったのがきっかけでした。それで給料を貯めて、ターンテーブルとミキサーを買ったんです」
実はDJについて知る前に、天啓とも言える出会いが田中さんの人生に訪れる。それは高校生のとき。当時所属していた軽音楽部の顧問の先生とのめぐりあいだ。
「ジョン・レノンみたいなメガネをかけた生物の先生だったんですけど、教師になる前は京都の放送局に勤めていて。放送局って月に一度、要らないレコードを廃棄するみたいで、そんなレコードを先生がもらってきて部室に置いてくれるんですよ。それをみんなで山分けしてね。高校生だしお金ないからレコード買えないんだけど、そこでもらえたからどんどん貯まっていくんですよ。それをカラーボックスに入れて家に置いておくんだけど、そのときにレコードを集める快感を知っちゃって(笑)。その後にマハラジャでDJの存在を知って、自分もDJをはじめるわけです」





古着を探すこととレコードを掘ること。
所属していたバンドは、とあるコンピレーションアルバムへの参加が決まっていたものの、リリース元のレーベルの倒産によりその話は白紙に。バンドブームも下火になり、音楽でご飯を食べることを一度諦めたという。当時大学生だった田中さんは、そこでアパレル企業への就職を決意する。
「東京にはいっぱい服があったと思うんだけど、ぼくは京都だから、やっぱり古着がスタンダードだったんです。北野天満宮とか東寺で古道具市が開催されていて、そこで古着を漁ってましたね。通っていた高校が私服通学だったこともあって、ファッションへの興味は高いほうだったと思う。みんなで競い合ってましたから。『501®は赤耳じゃなきゃダメ』とか、『スーパースターは金ベロでメイド・イン・フランスがいい』とか、高校生が言ってるんですよ(笑)。とにかく音楽と同じくらいファッションが好きで、音楽で飯食えないならアパレルがいいなって思って、大阪のアパレル企業の企画部に入社することになったんです」
この日も大好きな古着のお店に向かった田中さん。今回訪れたのは横浜にある古着屋「アンカー・ヴィンテージ(AnchoR Vintage)」。オーナーの篠田さんとは以前からの知り合いだったが、タイミングが合わず、ずっとお店に足を運べていなかったのだという。
「篠田さんとは、とあるヴィンテージのイベントで知り合ったんです。会うたびに古着の話で盛り上がって、ずっとお店に行きたいと思っていました。今日、ようやく来ることができたんですが、このお店は素晴らしいですね。上質なアイテムがたくさん揃っている上に、値段はかなり良心的。オーナーの人柄が表れた素敵なお店だと思います」
さらに古着の魅力について尋ねると、「やっぱり“出会い”じゃないですかね」と続けて答えてくれた。
「いいデザイン、いい形でも、自分のサイズに合わなかったらダメじゃないですか。そういう一期一会なところがいいのかなって。それに、過去につくられたものってなんか夢がある。昔の人が一生懸命考えて、未来の俺たちのためにこんなものを作ってたんだ! って。そんなアイテムに出会って、自分の体にフィットして、なおかつかっこよかったら感動するじゃないですか。いまはなんでもネット検索で出てくるけど、やっぱりそれじゃあつまらない。出会い頭の感動をぼくは求めたいですね」





アパレル企業に就職しつつも、音楽活動は常にキープし続けていた田中さんは、92年に自身のイベントを京都でスタートさせる。毎週木曜日のレギュラーパーティで、流れるのは映画のサウンドトラックのみだった。
「サウンドトラックってカバージャケットがかっこいいじゃないですか。中古レコード店では日本では公開されていない映画のサントラも売ってたりしていて当時は意外と安かった。もう完全にジャケ買いですね。映画音楽ってクラシックもあればファンクもあるし、ソウル、ディスコ、ボサノバもある。だから全然飽きませんでした。そういうジャンルに目をつけたのは世界的にも日本が早かったと思います」
ただ、そんなパーティをスタートさせつつも、「売れたい」「自分の名前を世に広めたい」といった欲はなかったという。「欲しいレコードを買って、それを誰よりも先にプレイしたい。ただそれだけ」と田中さんは当時を思い出しながら語ってくれた。
「やっぱり、20代の頃はレコードのことしか考えてなかった。当時はアパレル業から編集者へと転職をしていたんですけど、それでも給料のほとんどがレコードに消えてましたね。でも、他の人が欲しがっているレコードに興味はありませんでした。誰も見向きもしないレコードの中にいいものが潜んでいるんじゃないか? と常に思っていたんです。古着を探すのとちょっと似ているかもしれませんね。いまもそうやってレコードを探しているけれど、当時がむしゃらになって掘っていたのは、いまの音楽性の礎になってますね」

日本の音楽が世界へと羽ばたいた90年代。
京都で地道な音楽活動を続けていた田中さんは、東京で活躍するDJとの交流も深めていく。テイ・トウワ、小西康晴、コモエスタ八重樫、瀧見憲司といったアーティストを関西に招き、イベントを開催。その活動が自身のキャリアを一歩前進させることとなる。
「当時、テイ・トウワさんやピチカート・ファイブの小西さんは既に世界で活躍するアーティストでした。それで海外へ行ったときにぼくらのことを話してくれていたみたいなんです。『京都におもしろいやつらがいる』って。そしたらヨーロッパからわざわざ京都に会いにきてくれるDJが何人もいて、『オリジナルのトラックをリリースしないか?』と持ちかけてくれたんですよ。実は先のおふたりの助言で自分の曲の制作をスタートしていて、日本でのリリースよりも先にベルリンのレーベルからのリリースが決まったんです(笑)。ラッキーでしたね」
そんなことをきっかけに当時勤めていた出版社を退職し、東京に拠点を移した田中さん。フリーの編集者として仕事をしつつ、同時にDJ、ミュージシャンとして本格的な音楽活動をはじめる。アーティスト「FPM」の誕生だ。
「DJと編集って当然似ているんです。膨大な素材の中から、デフォルメしたい部分を切り取って世に伝えるということだから。ただ、編集の仕事をしながら音楽をやっていると、『あいつは音楽をナメてる』なんて言われたりもしました。でも、ぼくは全然気にしなかったですね。FPMって鼻に付くほどおしゃれな音楽やってるって言われてますが、高校生のときからドロドロでコアな音楽を聴いてきたし、それが自分のベースになっているのは変わらなかったから。逆におしゃれな音楽こそパンクだと思ってました」
90年代、日本の音楽シーンは80年代にも増して勢いがあったと田中さんは話す。メジャー音楽が大衆の気を引き、その陰で活動を行いながらも、「いま考えれば豪勢だった」と当時のシーンの裏側について教えてくれた。
「CDを一枚つくるのにレコード会社がいまでは考えられないくらいの予算を出してくれました。しかも、発売すれば、それがちゃんと回収できるほど売れた。渋谷系が華やかりし90年代は、CDがものすごく売れたんです。最初に話していた通り海外でのリリースも順調だったし、ファーストアルバムなんて新人なのにベルリン、ロンドン、アムステルダムまで行ってレコーディングしたんですよ。なんかバブル感じませんか?(笑)。日々いろんなライセンス契約のファックスが届いて、自分がいいと思ったものにはサインしていたんですけど、その中に『セックス・アンド・ザ・シティ』のサントラの契約書もあって。当時は『ポルノムービーかな?』なんて思っていたんですけど、その後何年かしたら日本でもブームになって。後にDVD化時に再び契約書が来て、あ、あれポルノ映画じゃなかったんだって。『オースティン・パワーズ』のサントラにもぼくの曲が収録されることになったり」
日本の音楽が世界へと羽ばたいた90年代。その要因について田中さんはこう説く。
「日本人はセンスやサンプルの切り取り方が上手だったんです。要するにエディットセンスがあったということ。それが新しかったんだと思います」





「イベントがあって横浜に来ると、必ずここに寄ってご飯を食べるようにしています。すごく美味しいんです」と、グルメな田中さんも太鼓判を押す横浜・中華街にある「山東」。本格的な中華料理を出すお店で、夜になると中華街の住人たちもここに食べに来るほど。横浜で音楽フェスがある時期は、たくさんのアーティストがこのお店に訪れるそうだ。
強欲な世代にチャンスを与えたい。
90年代から続ける音楽活動の流れを止めることなく、現在も年間120カ所はDJとしてステージに上がり、自身の楽曲制作はもちろん、数々のアーティストのリミックスやプロデュースも手がける田中さん。音楽活動行う上で、大事にしているのはどんなことなんだろうか?
「流行とかはどうでもよくて、自分が納得できるものを作り続けることが大事だと思っています。自分の得意なことをやるのは簡単なんですが、飽きてしまう。自分のフィールドを広げる意味でも、もっといろんなことに挑戦したいですね。誰も聴いたことのない音楽をつくりたいし、誰もやったことのないDJをやってみたい。やっぱり自分が常に楽しくて興奮できるかっていうことが大事ですね」
現在、田中さんの音楽のベクトルは“一生聴ける音楽”に向いているという。
「最近はようやく自分のことを冷静に見つめられるようになってきたし、マイペースに活動ができるようになってきました。50歳を超えて『一生聴ける音楽ってなんだろう?』って思うようになってきて、ダンスミュージックは基本刹那的なものだし、最先端を目指すものなんだけど、そういった時代や流行を超越する音楽って何だろうと考えるようになりました」
FPMでは一生聴ける音楽を追求しつつ、一方ではダンスミュージックをさらに掘り下げていきたいと田中さんは考える。
「『dododod(ドドドッド)』っていうダンスミュージックにひたすら向き合うプロジェクトもスタートしました。そこではひたすらクラブで革新的なダンスミュージックを鳴らしたいなと。これがあるからこそ今後のFPMとの活動と住み分けができるし、自分自身の役割がより明確になった気がしています。いまは昔みたいな明るい話が音楽業界には少ないし、やらなければならないことがたくさんあると思う。そういうときに自分のやりたい音楽がまだいくつもあるというのは幸せですよね」
そして田中さんは、今現在の20代に対して希望の念を抱いているという。
「これから20代になってくる子たちって、その親がFPMを聴いていた世代なんですよね。今の若者は何かにつけて無欲だって言われているけど、さらに下の世代の子供たちは逆にすごい強欲になるんじゃないかなって。ぼくの世代とすごい共通点があるような気がするんです。ぼくらもあらゆる面で強欲だったし。そういう新しい世代がつくる音楽というのを聴いてみたいし、もしすごい人が現れたら、ぼくはその人にいろんなチャンスを与えたいなって思っていますね」

「コンパス」はコンパクトなスポーツカーという感じ。
音楽のルーツや現在の想いを聞いてきた一方で、田中さんの普段について尋ねると、「クルマに乗るのが好き」だと教えてくれた。とはいえ、都心での生活にはクルマが必要なく、日常のなかで“あえて乗る”ことが多いという。
「お酒を飲んだりするのもぼくの仕事のひとつだったりするので、日常的にクルマを運転することはあまりないんですけど、クルマは大好きなんです。運転しているときだけはひとりになってゆっくりできるわけで、ぼくにとって特別な時間です。アルバムが完成したら、できあがったばかりの音源を、クルマを運転しながらチェックするのが自分の定番ですね。ちょうどアルバムの仕上げの作業となるマスタリングのスタジオが川崎にあって、その帰り道にいつも出来上がったばかりの曲をチェックしていました」
普段の運転中はなにか考え事をするというよりも、リフレッシュさせる効果のほうが強いと話す。
「音楽に耳を傾けるのもいいんだけど、あえて音楽はかけないで、自分の心をニュートラルにしてくれる時間にするときもある。運転しながら頭をリセットさせるというか。たまに都市部を離れて、クルマのある生活をしてみるのもいいかな? なんて思ったりもします(笑)。そうしたらジープに乗りたいなぁ」
田中さんが〈ジープ〉に抱くイメージ。それはどんなものなんだろう?
「実はうちの父親がずっと『ジープに乗りたい』って言っていたんですよ。そもそもジープって軍用車でもあるじゃないですか。タフで無骨、それに力強い走り。そういう部分に魅力を感じますよね。ぼくは古着が好きだし、ミリタリーものも大好きなんで、そういう軸のあるクルマにはやっぱり憧れます」
今回、田中さんに乗ってもらった「コンパス」は、〈ジープ〉の代表モデルのひとつである「グランドチェロキー」のデザインを継承しながら、街乗りに適したサイズが魅力のニューモデルだ。このクルマを運転して、田中さんはどう感じたのだろう?
「都市生活にフィットするサイズ感というのがいいですよね。小回りが効くし、Uターンする機会も多かったんだけど、回転半径もサイズと比例して小さい。それがすごく魅力的に思えましたね。すごく運転しやすかった。ジープは大きいから、運転のしやすさに関しては疑問があったんだけど、実際に乗ってみると、その不安はすぐに解消されました」
続けて、こんなことも話してくれた。
「コンパクトなスポーツカーという感じがしましたよ。乗り心地もいいし、居住性も抜群で、インテリアもいい。デザインも男らしいイメージもありつつ、洗練されたムードもあっていいですね」



己の力を信じることが大切。
デビューから20年以上経った現在でも、音楽シーンの最前線で活躍を続けるFPMこと田中知之さん。その活動の原動力はどんなものなのか? 自身にとってのスタンダードについて教えてもらった。
「無理をしないことですかね。スケジュールもそうだし、気分がのらないときとか、体調がすぐれないときは仕事に行かないとか。ズボラになるという意味ではなくて、自分の第六感を信じようということです。いらぬ先入観で仕事を選んじゃダメなのかもしれないけど、『なんかちょっと違うなぁ』と思ったら、ぼくはそれに従うようにしています。逆に『この人に会ったほうがいいかも』『ここに行ったほうがいいかも』って思ったら、そうするようにしていますし。これまで自分の勘を頼りに活動してきて、なんの根拠も理由もないんだけど、その気持ちに忠実に行動したほうが結果的によかったことが多いんです。だからまぁ結局は、己の力を信じることが大切なのかもしれませんね(笑)」
今回使用したクルマ
『Jeep® Compass Longitude(ジープ コンパス ロンジチュード)』
【主要諸元】
全長:4,400mm / 全幅:1,810mm / 全高:1,640mm / 乗車定員:5名 / エンジン種類:直列4気筒 マルチエア 16バルブ / 総排気量: 2,359cc / 使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(60ℓ) / 最高出力(kW / rpm):129(175ps) / 6,400(ECE)/ 最大トルク(N・m / rpm):229(23.4kg・m) / 3,900(ECE)/ 前2輪駆動 / 全国メーカー希望小売価格¥3,510,000~(消費税込)
Jeep® FREE CALL 0120-712-812
www.jeep-japan.com
Photo_Fumihiko Ikemoto
Text_Yuichiro Tsuji
Edit_Jun Nakada
Produce_Kitchen & Company