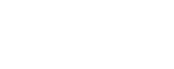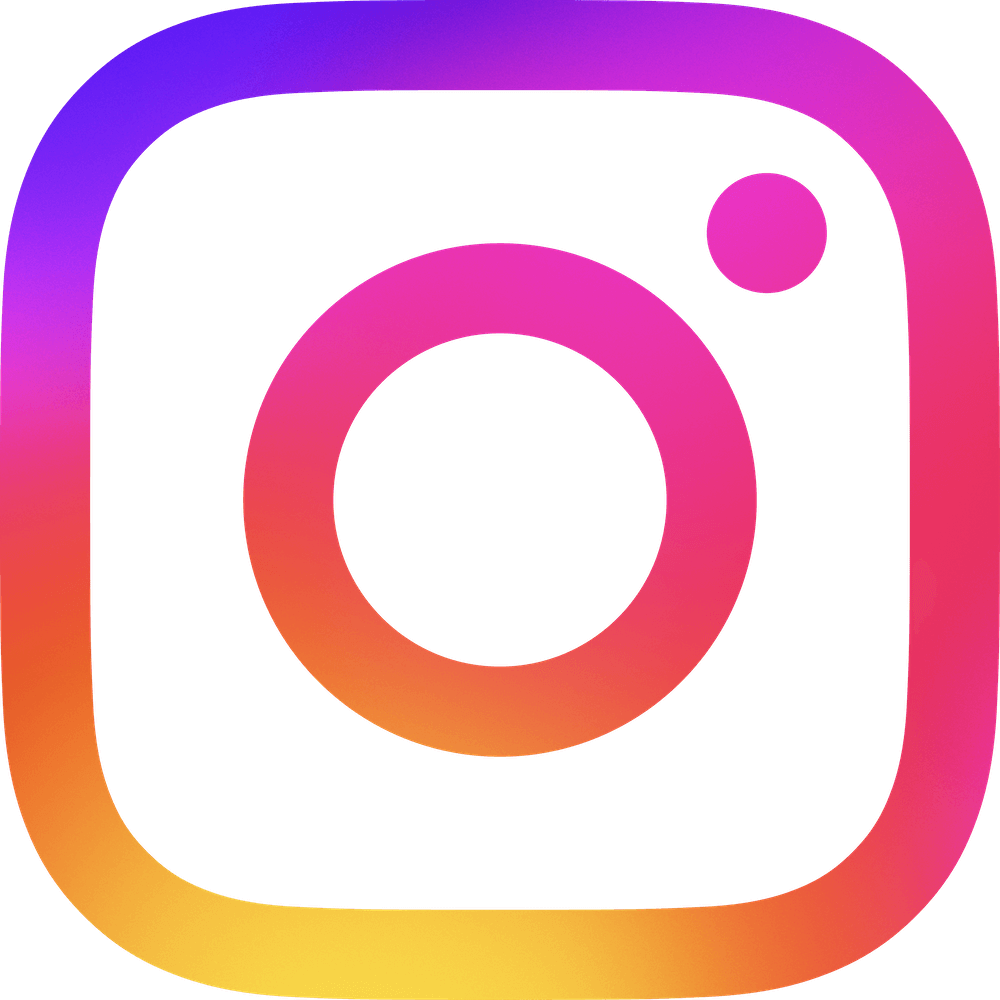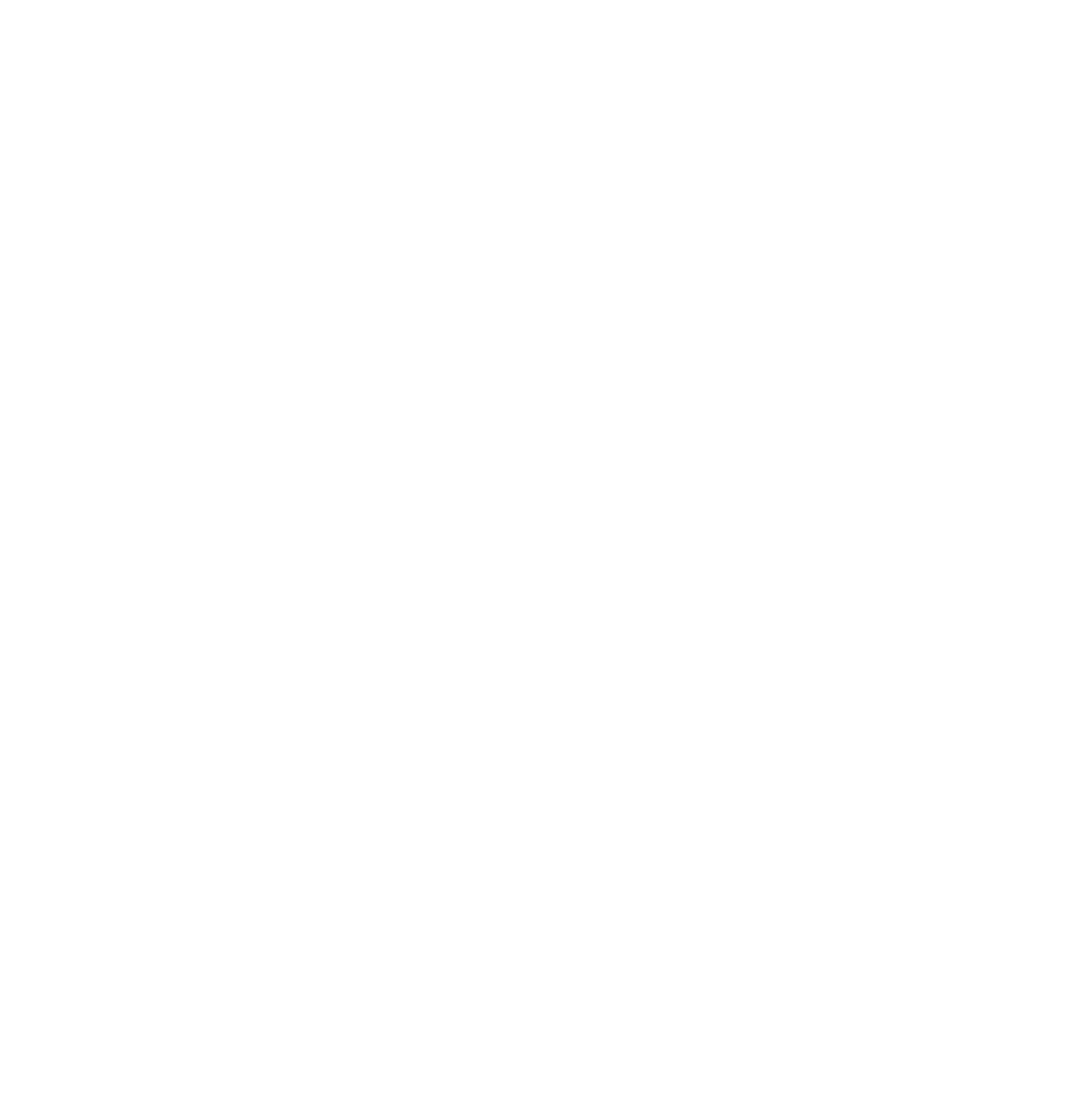My Jeep®,My Life. ボクとJeep®の暮らしかた。ミュージシャン・曽我部恵一
ジープを中心としたコミュニティ・プロジェクト「CREATIVE GARAGE」では、ウェブマガジン『フイナム』、J-WAVEのラジオ番組「Jeep® CREATIVE GARAGE」と連動して、「現代のスタンダード」をテーマに新しい創造のきっかけとなるアイデアや情報の数々をお届けしています。今回はミュージシャンの曽我部恵一さんが登場。多彩な音楽活動を展開する氏の原点、そして、知られざるクルマとの向き合い方に迫ります。


九十九里は、一番好きな海。


1992年の結成以来、街に佇む人々の物語を情景豊かな詩と透明感のあるメロディにのせ、多くの若者たちを魅了してきたロックバンド「サニーデイ・サービス」。曽我部恵一さんは、そんな90年代シティポップを代表するバンドのフロントマンとして、また一人のシンガーソングライターとして、今もなお精力的に楽曲を世に送り出しながらファンのみならず多くのアーティストにも影響を与え続けている。そんな氏の楽曲作りの原点にあるものとは。年に数回訪れるという千葉県の九十九里浜へクルマで向かいながら、語ってもらった。



「九十九里は、90年代にPVの撮影で来て以来好きになりました。憂いや寂しさというほどでもないのですが、九十九里一帯のマットな色彩や、砂浜がどこまでも長く続く風景に、どこか自分の音楽に通じるような虚無感を感じるといいますか。故郷の穏やかな瀬戸内海とはまた違った私情の入らない海。誰でも、日々、気持ちの高揚や落ち込みに持っていかれることってあると思いますが、そういうものが何もない『無』の心地よさを九十九里の海からは感じますね」
曽我部さんと九十九里を繋ぐのは、もちろん風景だけではない。「GROOVETUBE FES」という地元の音楽フェスと、それを主催する永野貴紀氏の存在も氏が定期的に九十九里を訪れる理由のひとつだという。


「ここは永野くんが週末だけ開けて友達とワイワイやってるというバー。僕も九十九里に来るたびに休憩場所として使わせてもらっています。手作り感があってマニアックなレコードやCDもたくさんあるんですけど、背伸びしてない感じが潔いし、オルタナだなぁと。フェスにしても、こういう店を作る人が主催しているというのがいい。規模は大きくないですが、地元の人たちが毎年楽しみにしている感じがとても魅力的。大きなフェスで多くのファンにアピールしていくのも大事なんですけど、そうではないローカルな規模で、限られた何人かに聞いてもらうための音楽というのも大事だなと。何度も出演させてもらいながら毎回学ばせてもらっていますね」

出会い、そして縁。曽我部さんが普段から無意識に大切にしているものが、九十九里にはあるのかもしれない。
「そう、結局、縁でしか物事は回っていかないので。何かもが起こるべくして起こっているし、人とも出会うべくして出会っていると思いますね」

音楽家としてのルーツは、パンクとの出会い。

曽我部さんと音楽との出会いについてもあらためて聞いてみた。すると、氏の音楽性を考えると少々意外にも思える答えが返ってきた。
「中学2年の頃、親戚がカセットテープにダビングしてくれたセックス・ピストルズを聴いて衝撃を受けました。それまではヒットチャートに入っているような流行りの音楽を聴いていましたが、雷に打たれたかのようにピストルズが突然僕の目の前に現れたんです。それからパンクバンドを結成して、ピストルズやクラッシュのコピーでライブをやったりしましたね。高校からはいろんな音楽を聴くようになり、現在に至るという感じなんですけど、今でも精神としてはパンクを初めて聴いたあの頃と変わっていないつもりです」
パンクから学んだもの。それは音楽に対する「姿勢」なのだと曽我部さんは熱を込めて語る。
「なんでもやってみようよ、ということなんですよ。恥ずかしがらずに好きなことを好きなようにやったらいいんじゃない? って、そうパンクがはっきり言ってくれた気がしています。ピストルズはわかりやすく『お前ら全員嫌いだ』的なことを歌っていてそこから勇気をもらいましたが、ジョン・レノンもボブ・ディランもよく聴くとそう言うことを歌っていることに気がついて、ロックやアート、そしてファッションにもどんどんのめり込んでいきましたね」

そうやって地元・香川での青春時代をパンクにどっぷり浸かりながら過ごした曽我部さんが次に目指したのは東京。大学進学を機に上京し、ミュージシャンとしての第一歩を踏み出す。
「大学がどうとかっていうよりもとにかく田舎を出たかった。東京のカルチャーに触れないと何も始まらないという感覚でした。出てからはとにかく遊びましたね。当時の渋谷にはレコード屋さんもたくさんあったし、雑誌の『宝島』で読んだようなものが全部あるし、まさに渋谷が文化そのものでした。もう最高でしたね。ただ、いざこの場所で自分がバンドをやる、と考えた時に、こんなに才能が溢れる街で自分がデビューするというのは無理なんじゃないかなって」

しかし1994年、インディーズでの活動を経て「サニーデイ・サービス」はメジャーデビューを飾る。
「レコード会社のディレクターに音源を気に入ってもらえてデビューしたんですけど、でもデビューしたからといって何かが変わった訳ではなかった。認められていないって初めて感じました。フリッパーズ・ギターの2人やオリジナル・ラブの田島(貴男)さんといった才能がある人たちがいる中、大したキャリアもなく、パンクの思想だけ一丁前な自分たちに一体何ができるんだと悩みましたね」
ターニングポイントは1996年にリリースしたサニーデイ・サービスのセカンドアルバム『東京』。大都市における当時の若者たちの心情や佇まいをリアルに映し出し、また当時の多くのリスナーが、上京、進学、就職、結婚といった人生の節目をともにしてきたであろう90年代を代表する名盤だ。
「初めてチャートインしたんですよね。30位くらいでしたけど。それで、『ああ、なんか、俺らの音楽聴いてくれている人がいるんだ』って、初めて実感しましたね。それはもう、嬉しかったですよ」

その後、2000年にサニーデイ・サービスは一度解散するも、ソロや曽我部恵一BANDなどの活動を経て2008年に再結成。現在は2004年に設立した自身のレーベルROSE RECORDSの代表として、また一人のアーティストとして、衰えることのない創作意欲とともに経営と音楽活動の両方を情熱的にこなしている。
「いつもスランプだとも思うし、常に悩んでる。でも曲を出し続ける、という感じ。そうやって日々途切れず作る感じが自分には向いている。作品ができた時の満足感というのは若い頃から変わらないですし、リスナーのみなさんは『お前が好き勝手やってることにお金を払ってるんだよ』って思ってくれていると思うので。だから魂を込めて、命をかけて好き放題、わがままをやり通さないと。それがアーティストのあるべき姿だと思いますし、パンクから学んだことでもあります。たまには守りに入りたいなと思うこともありますけどね(笑)。精一杯、とにかく行けるところまで行って倒れた姿を見てもらう。それが自分の美学であり、ファンに対する責任だと思っています」
レネゲードは自分にとって理想のクルマ。

九十九里から高速で東京に戻りながら、クルマとの付き合い方についても語ってくれた曽我部さん。日々、とめどなく曲を作り続ける中で、完成前にクルマでサウンドチェックを行うのがルーティンなのだそう。
「完パケ前は必ず運転しながら作った曲をかけます。1時間分曲があるなら、1時間のドライブコースをぐるっと回って、帰ってきて直してまた出る。前作もそうやって何周もしました。クルマって、人間が発明したいろんなものを合体させて日常生活に落とし込んだ究極のものだと思うんです。そういう場所で“響く”かどうかは大事。山や海でよく聴こえるのは当たり前なので、むしろ歌舞伎町を通りながらどう聴こえるかが大事ですね」
もちろん、自身の曲以外も聴く。音楽とクルマは氏の中で常にリンクしているものだ。

「気になったやつはジャンル問わず何でも聴きますよ。常にいいのがないかなと探していますしね。最近はあらためて、ジミヘンはドライブミュージックとしても最高だなと。アメリカの音楽って、やっぱり車社会の音楽だなという感じがしますよね。ビートルズも最高。『オー! ダーリン』とか『ゴールデン・スランバー』とか、なぜかクルマだとポールの曲がいいんですよね。クルマはポール、家ならジョン(笑)。それと、この間次女と首都高に乗りながら小西(康陽)さんのソロプロジェクトである『ピチカート・ワン』の最新作を聴いたら、暗闇に都会のきらめきが浮かぶ夜の首都高にすごくハマって、沁みましたね」

今回、曽我部さんに乗ってもらったのは「レネゲード(TRAIL HAWK)」。気に入っているのは、何と言ってもそのデザイン性なのだという。
「丸みがあって、それでいて正方形に近い形のクルマが昔からすごく好きで。だからこのレネゲードは僕にとって理想的な形。いい意味でおもちゃっぽいというか、メカっぽいというか、男心に響くデザインですよね。後ろのブレーキランプのバッテンを初めて見たときも『これはやばすぎる!』と(笑)。アメリカの田舎で見かけるような、割れたランプにそのままガムテープを貼ってる感じからインスピレーションを受けているんじゃないだろうか、なんて勝手な想像を掻き立てられたり。ダントツにすばらしいデザインですね」

〈ジープ〉に対しては、子供の頃から憧れがあったという。
「〈ジープ〉は昔、知り合いのお兄さんが乗っていたのを見てかっこいいなと思って、それ以来ずっと憧れのクルマでした。もともと軍用で、それが街にいる感じがカッコイイなと。レネゲードのように現代的なデザインになった今も、そういう趣や遊び心が随所に残っていて好きですね。乗り心地も程よくどっしりとしていて、運転していて本当に気持ちがいいクルマだと思います」


やりたいことをやり通す。それがアーティストとしての矜持。
真摯に作り続ける音楽に対しても、また日々をともに過ごすクルマに対しても、どこか共通したこだわりを滲ませる曽我部さん。氏が何かに向き合うスタンスは、この企画恒例となった人生を送る上でのスタンダードにもつながっている。
「さっき話したことに近いですが、周りからわがままだと思われたとしても自分がやりたいと思ったこと、いいと思ったことを貫き通す。それがアーティストとして一番大事だと思っています。それこそ、パンクの精神ですね」

今回使用したクルマ
『Jeep® Renegade TRAIL HAWK(ジープ レネゲード トレイルホーク)』 ボディカラー : ソーラーイエロー C/C
【主要諸元】
全長:4,260mm / 全幅:1,805mm / 全高:1,725mm / 乗車定員:5名 / エンジン種類:直列4気筒 マルチエア 16バルブ / 総排気量: 2,359cc / 使用燃料:無鉛レギュラーガソリン / 最高出力(kW/rpm):129(175ps)/ 6,400(ECE)/ 最大トルク(N・m/rpm):230(23.5kg・m)/ 3,900(ECE)/ 4輪駆動(オンデマンド方式)・電子制御式9速オートマチック / 全国メーカー希望小売価格¥3,456,000~(消費税込)
Jeep® FREE CALL 0120-712-812
www.jeep-japan.com
Photo_Shinji Serizawa
Text_Kai Tokuhara
Edit_Shinri Kobayashi
Produce_Kitchen&Company