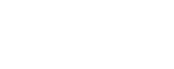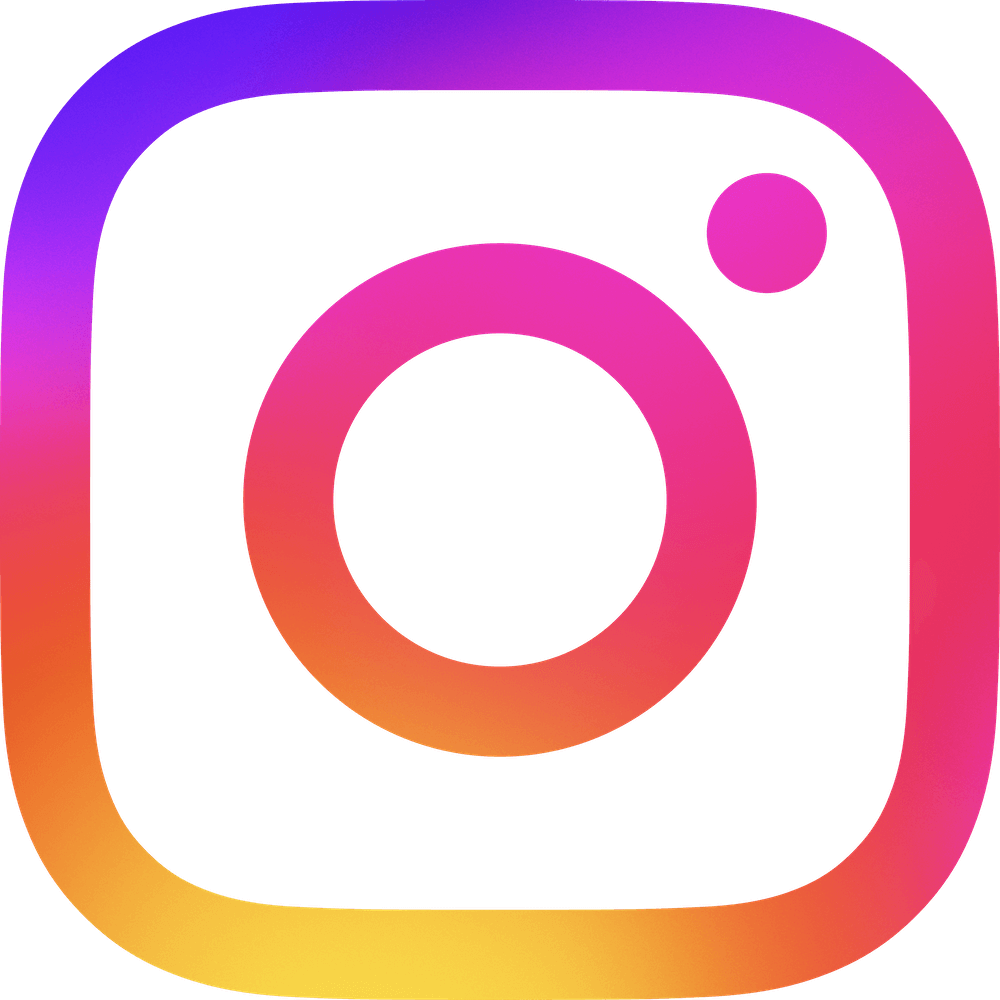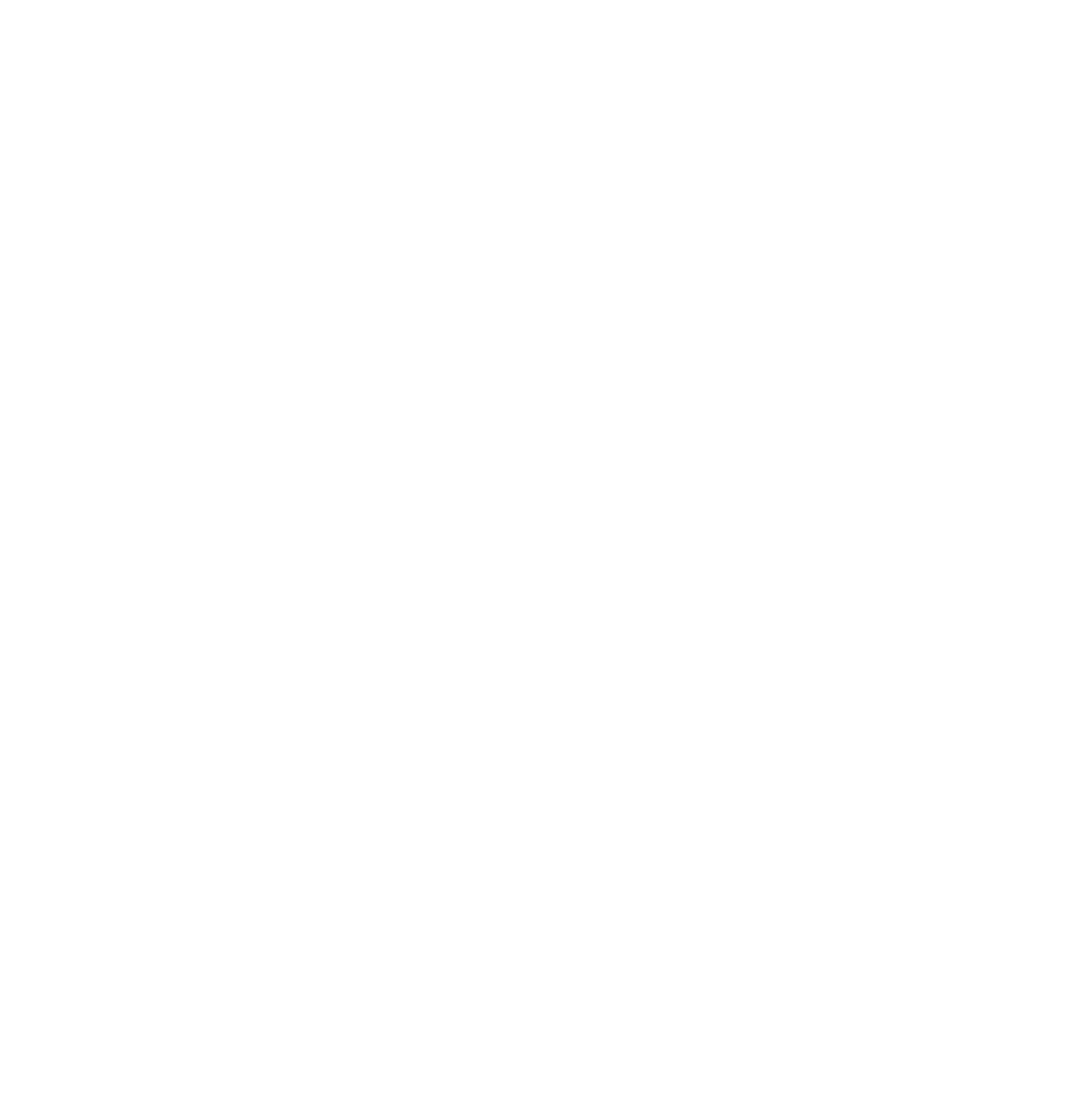Jeep® 協賛の『世界の野球グローブ支援プロジェクト』に、日米で活躍した名ピッチャー・岡島秀樹さんがエールを送る!
今年からJeep® は、世界の子どもたちに野球用具を贈る『世界の野球グローブ支援プロジェクト』に協賛。そこで今回は、日米で活躍した名ピッチャーであり、ボストン・レッドソックス時代にチェロキーを愛用していた岡島秀樹さんに、これまでの野球人生とこれからの夢、そしてプロジェクトへの想いを聞いた。
読売新聞社が独立行政法人国際協力機構(JICA)の協力を得て、2016年度から実施している『世界の野球グローブ支援プロジェクト』。このプロジェクトでは、用具が無くて野球ができないという世界の子どもたちにグローブやボール、バットなどを贈るとともに、「野球指導のためのプログラム」(プロコーチを派遣し、現地の子どもたちに野球の実技指導)を提供している。その結果、2018年度は4902個もの用具が集まり、寄贈先は世界15ヵ国へと拡大。開発途上国における野球の普及と、野球を通じた青少年教育の機会創出を目指している。そして、その理念と活動をさらに飛躍させるべく、今年からJeep® もこのプロジェクトに協賛することとなった。
『世界の野球グローブ支援プロジェクト』はWEBサイトから寄付する方法以外にも、全国のジープ正規ディーラーに専用収集BOXを設置(野球用具収集期間は、2019年7月1日(月)から2019年10月31日(木)まで)。そちらから寄付した方には、『UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)』とJeep® のコラボによる、限定“ラバーブレスレット”がプレゼントされる。
▲UNDER ARMOUR × Jeep® のオリジナルラバーブレスレット
このプロジェクトをより多くの人に知ってもらうにあたって今回は、読売ジャイアンツ、北海道日本ハムファイターズでプレーしたのち、メジャーリーグのボストン・レッドソックスなどでセットアッパーとして活躍した岡島秀樹さんにインタビュー。実は、岡島さんはボストン時代に『Jeep® Cherokee(ジープ チェロキー)』を愛用し、当時、助けられたという思い出も。引退から3年、いまは野球解説者として新たな道を歩んでいる岡島さんに、これまで歩んできた野球人生とこれからの夢を語ってもらうとともに、『世界の野球グローブ支援プロジェクト』へのエール送ってもらった。
エースとして臨んだ甲子園での敗北。そこから野球に目覚めた
二つ年上の兄の背を追い、小学校2年生から地元少年野球チームで野球を始めた。
「京都市内でも比較的、田舎の伏見区の淀で生まれ育ちました。兄が少年野球チームに入っていて、それについて行っているうちに、“一緒に、どう?”という感じで、野球を始めることになりました。実は野球とか、全然、興味なかったのですよ。でも、外で走ったり、跳んだり、体を動かすことは大好きで、家の庭でビニールのボールを使って、野球のまねごとのようなことはしていたので、すんなり溶け込むことはできましたね」
左投げということで、ポジションはだいたいピッチャーか外野。小学校6年生のときには、エースを任せられるようになった。
野球に目覚めたのは、地元の東山高校に進学し、2年の春にエースとして甲子園出場したときからだという。小学校で所属したチームの中学の部で、やはりエースとして活躍した岡島さんは、2年のときに全国大会出場を果たすなど実績を残し、卒業時には、近隣の複数の高校から誘いを受ける注目のピッチャーに成長していた。
「2年のセンバツ出場は、めぐり合わせがよかったからだと思います。それで、初戦、1点差で勝つものの、2戦目で負けてしまうのです。京都府では負け知らずだったのですが、全国のレベルの高さを思い知らされました。それで、もっともっと力をつけなくてはいけないと。それまで、野球をやっているということで、卒業アルバムなどに漠然と『将来の夢 野球選手』と書いたりしていたのですが、甲子園で負けてから、本気で“プロ野球選手になりたい。なるんだ”と思うようになりました」
メジャーでの苦悩の末に学んだ、冒険する気持ちと情熱の大切さ
1993年のドラフト会議で、読売ジャイアンツから3位指名を受け、夢はかなう。家族は全員、阪神タイガースファン。ところが、交渉権を得たのは、ミスターこと長嶋茂雄監督(当時)。「長嶋監督のジャイアンツなら」と入団を喜んでくれた。
「僕が入団したころのジャイアンツというと、3本柱(槙原寛己、斎藤雅樹、桑田真澄)が確立されていて、続いて宮本(和知)さん、水野(雄仁)さん、木田(優夫)さんといった、そうそうたるメンバーがいるわけですよ。一番年が近いのが石毛(博史)さんで、それでも5つ上です。もう、気遣いが大変でしたね。当時は、スタッフの数も少なくて、マッサージもしてもらえない。アイシングは自分でしていました」
ボールを放す瞬間に、バッターから目をそらす独特のピッチングフォームは、ときにコーチから「改造」を求められることもあった。
「コーチの指示はチームの方針でもあるので、従わないといけません。それでキャンプのときなどに試してみるのですが、どうもしっくりこない。一方で、“自分のピッチングフォームは貫き通すべきだ”と応援してくれる人もいる。それはありがたかったですね。結局、プロの世界は結果がすべてですから。成績が残せるようになると、なにも言われなくなりました。自分のピッチングフォームを貫き通してよかったと思います」
日本球界では、先発から中継ぎに転向し、抑えとして胴上げ投手も経験した。「このままジャイアンツでプロ野球生活を終える」と思っていた岡島さんの目の前に、メジャーという思ってもみなかった選択肢がふいに浮かび上がってくる。北海道日本ハムファイターズへの移籍をきっかけに。
「当時のファイターズの監督は、トレイ・ヒルマンさんで、メジャーから帰ってきた新庄(剛志)さんが所属していて、メジャー流の野球をしていたのです。とにかく、ベンチの中が明るい。負けても、新庄さんが、“あしたや、あしたや。きょうは門限なしや”って。もちろん門限はあるのですが。ジャイアンツだとそういうふうにはいかないわけですよ。とにかく勝つことが使命づけられていますから。“ああ、こういう野球もあるんだ”と。新庄さんには、“オカジー”っていつも呼ばれていたのですが、“オカジー、おまえ絶対メジャーに向いているよ”と言われて、“メジャーもありかな”と思うようになりました」
2006年のオフ、フリーエージェント(FA)の権利を行使し、ボストン・レッドソックスと3年契約を結び、海を渡る。待ち受けていたのは、メジャー初登板、初球ホームラン被弾という、厳しい現実だった。
固いマウンド、滑りやすいボール、長距離の移動、日本では例のない10試合以上の連戦、話には聞いていたが、実際に経験してみて、初めてその大変さが身に染みた。辛いとき、しんどいときに、支えになってくれたのは、家族、そしてなんでも打ち明けることができる通訳だった。試合を重ね、気がつくと、メジャーの野球になじんでいる自分がいた。いつの間にか、本物のメジャーリーガーとして認められていた。
「やはり、メジャーでは、冒険する気持ちがないとやっていけません。自由の国アメリカでは、野球はチーム競技であると同時に、個人競技でもあるのです。成績がすべて。契約社会だからといって、日本のように契約したら1年間、なにもしなくても大丈夫というのではなく、試合で1球も投げないうちにクビになることもある。実力主義なのです。とても厳しいけれど、水が合いました」
次ページ:【ボストンでの暮らしにはかかせなかったJeep®】