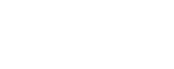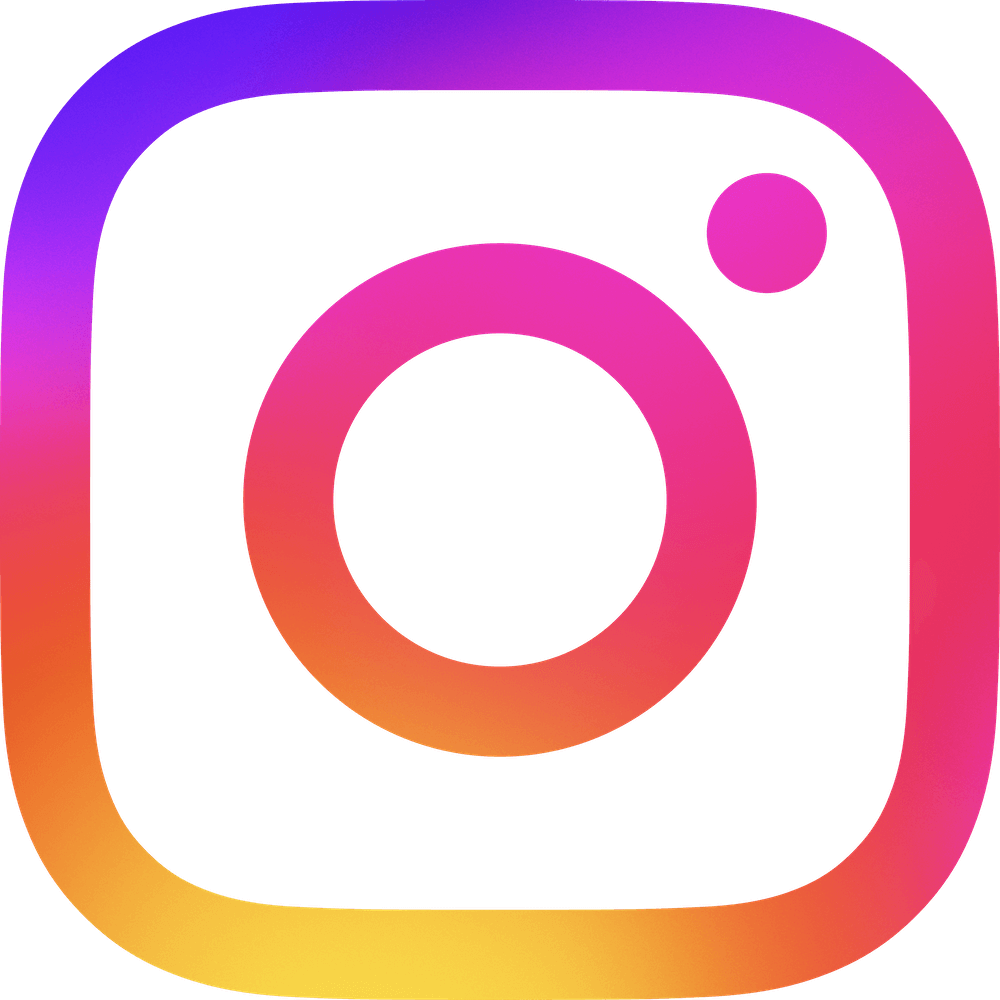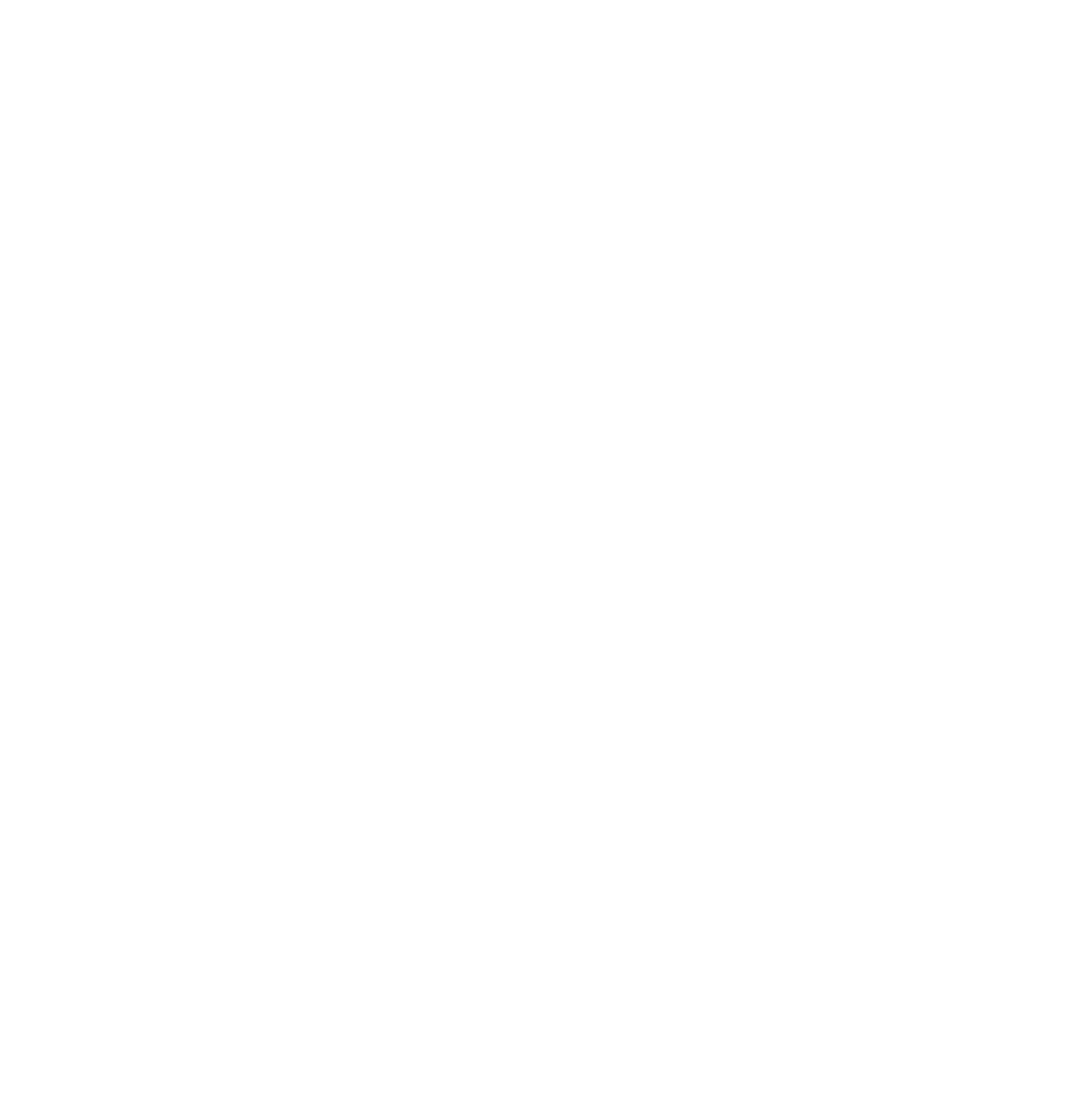Real Tabi with Jeep 〜Jeepと行く、日本の“こころ”を探る旅〜〈静岡県〉
山海の恵みを享受する“ふじのくに”で夜空に咲いた希望の花
自由、冒険、本物、情熱──。4つのDNAを持つJeepを駆って、日本という地が持つ“こころ”を解き明かす旅へ。日本の花火発祥の地といわれる静岡の地を訪ねて。
今回ご紹介した静岡の旅をYouTubeでお楽しみいただけます。
穏やかな気候と雄大な自然の中
富士山の美景を満喫
秋晴れの空の下、“ふじのくに”と称される静岡を『ジープ レネゲード リミテッド(Jeep Renegade Limited)』で訪れた。標高約300mの丘陵地、日本平へのドライブでは広大な茶畑のグリーンと駿河湾の深いブルーのコントラストが富士山に彩りを添えていた。
▲沿道に茶畑が続く日本平さくら通りをドライブすれば、富士山と駿河湾の絶景を一望できる。
富士山の南側に広がる駿河湾は最深部が2,500mに達し、日本で最も深い湾として知られている。独立峰として日本一の高さを誇る富士山とともに静岡を代表する景観だ。富士山から流れ込む雪解け水と、湾内を還流する黒潮の恵みとの相乗効果でアジ、サバ、イワシ、カツオ、シラス、サクラエビ、タカアシガニなどさまざまな魚介が水揚げされ、豊かな海の幸が訪れる人をもてなしてくれる。
この地を進むと、時に優雅に、時に雄大にそびえる富士山の多彩な表情に出合うことができる。かつての東海道「由比宿(ゆいしゅく)」と「興津宿(おきつしゅく)」の間に位置する薩埵峠(さったとうげ)では、歌川広重が「東海道五十三次」に描いた構図と同じ富士山を目にすることができた。眼下に広がる海とその向こうにそびえる富士の美麗な姿は、険しい峠をようやく越えた旅人たちにとって、疲れを吹き飛ばすほどの忘れえぬ絶景であったに違いない。
▲雄大な富士山と駿河湾を望む静岡の旅の要所、薩埵峠(さったとうげ)。
車窓から飛び込んでくる富士の絶景と駿河湾の海の幸に、心もお腹も満たされたら、「オクシズ」の愛称で近年、注目が高まっている山間部へと足を延ばしたい。スリリングな吊り橋や風情ある温泉が多い奥大井のエリアは野趣あふれる秘境の地。眩い新緑や色鮮やかな紅葉、南アルプスの残雪など、一年を通じて美しい風景が待っている。
▲全長258m、幅員約2mの井川大橋は車でも通行可能な吊り橋。コンパクトボディの『Jeep Renegade Limited』なら難なく走行できる。
▲静岡県最南端の御前崎。ロングビーチ沿いの県道357号線では、太平洋に沈む夕日を眺めながらのドライブが楽しめる。
名もなき旅人から徳川家康公まで
文化を築いた先人たちに想いを馳せて
江戸の日本橋から京の都までを繋ぐ東海道にあった53の宿場のうち、静岡には半分に近い22もの宿場が存在する。「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と唄われ、東海道中の難所の一つといわれた大井川越えの様子を知ることができる島田宿を訪れた。幕府の方針によりあえて橋を架けなかったという大井川のほとりに佇むと、想像以上の川幅と急な流れが目の前に迫ってくるようだ。当時、川を渡るためには川越人足(かわごしにんそく)の肩にまたがるか、連台に乗るかしか方法がなく、渡し賃は川の深さによって変わるため天候にも左右されたという。多くの人々や物資とともに東西の文化もまた、大井川を渡って伝播していったのだろう。
▲島田宿大井川川越遺跡では江戸時代の町並みが再現・保存され、川会所や番宿といった当時の川越しの様子を今に伝える。
静岡を語る上で忘れることができない歴史上の人物といえば徳川家康公だ。幼年期、壮年期、晩年を現在の静岡市街地にあたる駿府の地で過ごしたという。壮年期と晩年に自身の拠点と定めた駿府城や、遺言により遺体が葬られ全国の東照宮の創祀となった久能山東照宮など多くの遺構や記録が残されている。
▲徳川家康公を祭神として祀る全国東照宮の創祀、久能山東照宮の御社殿。元和3(1617)年に創建され、極彩色の御社殿は江戸初期の代表的建造物として国宝に指定されている。
▲久能山東照宮の拝殿に彫刻された「司馬温公のびん甕割り(しばおんこうのかめわり)」。子どもの命を救うため貴重な甕を迷わず割った中国の学者、司馬光の故事になぞらえ、生命の大切さを伝えている。
▲久能山東照宮の随所にあしらわれている徳川家の葵の紋のうちの3ヶ所は、紋の上下をあえて逆にした「逆さ葵」。これは完成した後は朽ちるのみという考え方から、未完成を表現したものと考えられている。
「駿府政事録」に慶長18(1613)年8月、イギリス国王の使節が駿府城の家康公を訪ね、花火を献上したという記述がある。この時に家康公が見た花火は黒色火薬を筒に詰めて火の粉を吹き出させた「立ち火」と呼ばれるものと考えられている。これを機に、家康公がお抱えの鉄砲隊に命じて観賞用の花火を作らせたことが日本における花火の起源だという。また、藤枝市の朝比奈川沿いでは、当時の手筒花火を彷彿とさせるロケット花火を櫓(やぐら)から打ち上げる伝統行事が現在も受け継がれている。
▲高さ約20mの打ち上げ櫓(やぐら)。ここから狼煙(のろし)が発達したものといわれるロケット花火「朝比奈大龍勢(あさひなおおりゅうせい)」が打ち上げられる。
伝統と未来を照らす美しい花火
“リアル”な感動に出合う
日本の花火文化のルーツともいえる東海・静岡エリア。現在でも静岡県は、花火大会が盛んだという。藤枝市を拠点に、明治37(1904)年の創業以来、花火業界を牽引してきたのが株式会社イケブンだ。
「私は幼い頃から地元静岡で花火に親しみ、憧れ、この会社で花火師になりました。イケブンでは、これまでの花火にはなかった水色やレモン色といったパステルカラーの花火製作やデジタル制御による点火など、新しい花火技術を開発してきました。残念ながら今年の夏は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため多くのイベントが自粛となってしまいましたが、小規模のものから少しずつ再開し、お客様にも喜んでいただいています」と語るのは、イケブンの花火師で若手のリーダー格である瀧村元晶氏だ。
▲株式会社イケブン 花火師 瀧村 元晶氏
瀧村氏の言葉を受け、ティツィアナ・アランプレセは、「日本の花火には、その名の通り花のような美しさがあります。外出もままならないこんな世の中だからこそ、自然の中に集い、みんなで空を見上げ、花火で幸せな気持ちを共有したい……。そんな思いでJeepオーナーのためのオリジナルドライブイン花火大会『Jeep HANABI 2020』を企画し、イケブンさんに花火の製作をお願いしました」と語る。
▲FCAジャパン株式会社 マーケティング本部長 ティツィアナ・アランプレセ氏
一度の大会で数千発が打ち上げられることも珍しくない花火は、職人によって一玉ずつ複数の工程を経て丁寧に作られる。まずは「星掛け」。「星」とは花火の中に詰まっている火薬の玉のこと。直径2〜3ミリの芯と薬剤を回転式の釜に入れ、ガラガラと回しながら大きくしていく。
▲釜を回転させながら配合された薬剤を少しずつまぶす作業を繰り返す「星掛け」。花火の色の決め手となる作業だ。
一度星掛けをしたら天日で干し、この作業を20回ほど繰り返したら次は「玉込め」だ。ボール紙でできた半球状の玉皮に星と割薬を詰めていく。どの星をどんな順番で詰めるかで打ち上げた時の美しさが決まるため、職人の技と感性の見せ所とされる。ぎっしりと火薬が詰め込まれた二つの半球を貼り合わせたら完成だ。花火大会は夏場に集中するため、製作作業は冬のうちに近隣の農家の手も借りて集中して行われる。
▲花火の色を決める火薬の玉の間に、空中で花火を割るための火薬を詰めていく「玉込め」。どの順番で詰めてどんな花火にするかの設計図は職人の頭の中にあるという。
「最近では、落下した玉皮が自然に還りやすいように水溶性の素材を採用するなど、環境への配慮も欠かせません」という瀧村氏に、アランプレセも共感の意を示す。
「自然を楽しむからには、自然を守り、共存していくことが大切です。Jeepも従来のガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッドモデル車を発表しました。二酸化炭素を排出しないゼロエミッション走行が可能になったことに加え、より静かで力強い走りを実現したことで、これまで以上に自然の息吹が体感できます」
10月の終わり、富士山麓にてドライブイン花火大会『Jeep HANABI 2020』が開催され、会場には多くのJeepが集まった。約30分間にわたり2,700発を超える豪快な花火が次々と打ち上げられ漆黒の夜空を彩った。
▲『Jeep HANABI 2020』は車に乗ったまま花火を楽しめるドライブインシアター形式で開催された。
頭上を覆い尽くすかのような10号玉や、カラフルな花火が連発で打ち上げられるスターマインなど、色鮮やかな花火が車内から見上げる人々の笑顔を誘った。中でも一番の見せ場である、Jeepのセブンスロットグリルをかたどった瀧村氏入魂の花火が連発で打ち上がると、会場は感動の渦に包まれた。
▲クライマックスでは、Jeepのアイコンともいえるセブンスロットグリルを表現したダイナミックな花火が連発で打ち上がった。
花火の見事な色彩や身体に響き渡る音、きらびやかな光はどんなにオンラインイベントが広まった今日でも、自然の中でなければ味わうことのできない“リアル”な迫力だ。かつて徳川吉宗公も、大飢饉とコロリ病(悪疫)による死者の霊を慰め、悪病退散を祈念するために江戸・両国の川開きで花火を打ち上げたとされている。今回の新型コロナウイルス感染症拡大の折も、全国の花火業者が同一日時に花火を打ち上げ、人々を元気づけた。先の見えない不安な日々が続くからこそ、自然の中に集い、みんなで空を見上げ、花火で幸せな気持ちになる……。高揚感を共有した静岡の夜もまた、未来へと羽ばたく原動力となったのではないだろうか。次なる新しい日常の中へ、Jeepの旅はまだまだ続いていく。
▲焼津市 笛吹段公園から望む夜景
●瀧村 元晶(たきむらもとあき)
株式会社イケブン 花火師
イケブンは明治37(1904)年の創業以来、花火業界のパイオニアとして、新たな花火技術を開発し続けている。瀧村氏は同社の伝統と技術、そして5代目社長である故池谷光晴氏の思いを継承する花火師の若手リーダー格。
※役職、肩書きは取材時のものです。
●ティツィアナ・アランプレセ
FCAジャパン株式会社 マーケティング本部長
ナポリ東洋大学で学んだ後、奨学生として来日。九州大学大学院修了。帰国後、日本の自動車メーカーの現地法人およびフィアット グループでの勤務を経て、2005年から現職。