旅の発見とは、 自分の目や足でこそ得られるもの
情報を入手しにくい時代の旅を知っているから、
“あまり人の手のついていないもの”に惹かれる

「GO OUT CAMP」と称し、読者ミーティング的に始まった主催イベントは年々スケールアップし、今年「GO OUT JAMBOREE 2012」と改称して開催。会場となったふもとっぱらキャンプ場は、広大な敷地を自由に使える寛大さと、トイレ、水道などの基本施設が整っていることで人気のキャンプ場としても知られている。
(c)Fumihiko Ikemoto
エディターとして、日本の雑誌文化を牽引してきた石川次郎さんの旅人生の始まりは、1964年。これは日本人が世界への扉を自由に手に入れられるようになった年であり、奇しくも石川さんが人生の新しいスタートを切った年でもある。
「大学卒業後、まずはトラベル・エージェントに就職をしました。理由はただひとつ、世界を見てみたかったから。同じ年に海外旅行が自由化になり、誰もが世界へと旅立てる時代が到来したんです」
つまり石川さんのキャリアは、”旅”を最優先してスタートさせたのである。
「けれどすぐに挫折してしまいました。海外旅行の自由化がスタートして、自由な旅をしたかったのに、ツアーコンダクターとはお客様の行きたいところを案内するのが仕事でしょう。それが向いていなかった。たった2年で辞表を出して、その後、以前から縁があって誘われていた平凡出版(現マガジンハウス)の編集者となったんです」
配属先は、当時一世を風靡した『平凡パンチ』編集部。そこで、数少ない海外旅行経験者だった石川さんに白羽の矢がたつ。
「海外取材担当となり、6ページ×10週間分の材料を取材しに行くことになったんです。選んだ行き先は、あの頃ほとんどの若者にとって唯一の外国だったアメリカ、NY。かつて先輩の編集者は、”これからは、編集者も海外へ行ける時代になるけれどね”と言っていました。本当にそんな時代がやってきたんです」
とはいえ、今のように取材のコーディネーターがいるわけでもないし、ガイドブックすらない。そんな中、石川さんは自らのアイデアと機転で情報を集め、取材を行なっていった。
「国内で情報など全く手に入れられないから、すべて向こうで仕入れなければなりませんでしたよ。ソースは情報誌や、現地の新聞、そしてイエローページの広告も貴重でしたね」
その街で何が起こり、何があって、どんな業種が勢いがあるのか。石川さんはそれを、現地の人たちが頼りにしている情報ツールと同じ物を使って調べ、見つけ、自らの足で確かめていったのである。
「自分の目や耳、足で手に入れなくてはリアルな発見はない。だから、街も本当にくまなく歩きました。性分として、調べなくてはいられないというのもあったかな(笑)。NYでは、面白いと思った通りにある店舗をすべて網羅してページにしたりしました」
「かなり貪欲だったよね」と当時を振り返る石川さん。この貪欲な取材から生まれたページが好評を博し、ヨーロッパ編へ続く。自分で情報を探し、見つけ、網羅してどんどん発信していく。それは自分の旅のスタイルと通じているのだという。
「旅とは非日常で知らない自分に出会える、という人もいると思いますが、僕の場合はそうではない。たとえ旅であっても自分から離れることはないんです」
誰かの判断など関係ない。自分のアンテナに引っかかる存在を追求する。それが石川次郎流の旅なのである。
その後アメリカ、ヨーロッパを経て、アジアも深く網羅してきた石川さんだが、昨年彼のアンテナを激しく触発させた場所があった。それは、47年ぶりに訪れた場所で、旅の重要性を再発見させてくれたのだとか。
「47年ぶりにドイツのベルリンに行ったのですが、とてもエキサイティングな街になっていた。しかも、かっこいいのは旧西ベルリンではなく、かつての東ベルリンだったのにも驚きました。ギャラリーも、クラブもミュージアムも、感度が高いのは東に多く見られる。社会主義時代の暗黒の象徴だったものが今、最先端のカルチャーを牽引している。時を経て街がこれほど変わるんだという事実が衝撃でした。それを肌で感じられるのも旅の醍醐味でしょう。やっぱり、旅はしなくちゃなと思いましたよ。プライベートの旅でもメモしまくるし、ストリートを調査したりしちゃいますね。旅にオンとオフの区別がないのは、あたりまえの事なんです(笑)」
旅を愛し、寄り添ってきた石川さんにとって、理想の旅とはどんなものなのだろうか。憧れの旅人として挙がった名前は、そのオリジナリティで古今東西の人々を惹きつける人物だ。
「あらかじめ到着を設定しないで出かけるような旅に憧れますね。すべてがいきあたりばったりであるようなスタイルというのは、旅の本質でもあると思うんです。いつか、目的もなくさまようような旅を自分もしたいな。ゲーテや老子も同じようなことを言っていたそうですよ。昔も今も、似たようなことを考えている人はいるんですね」
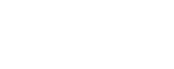






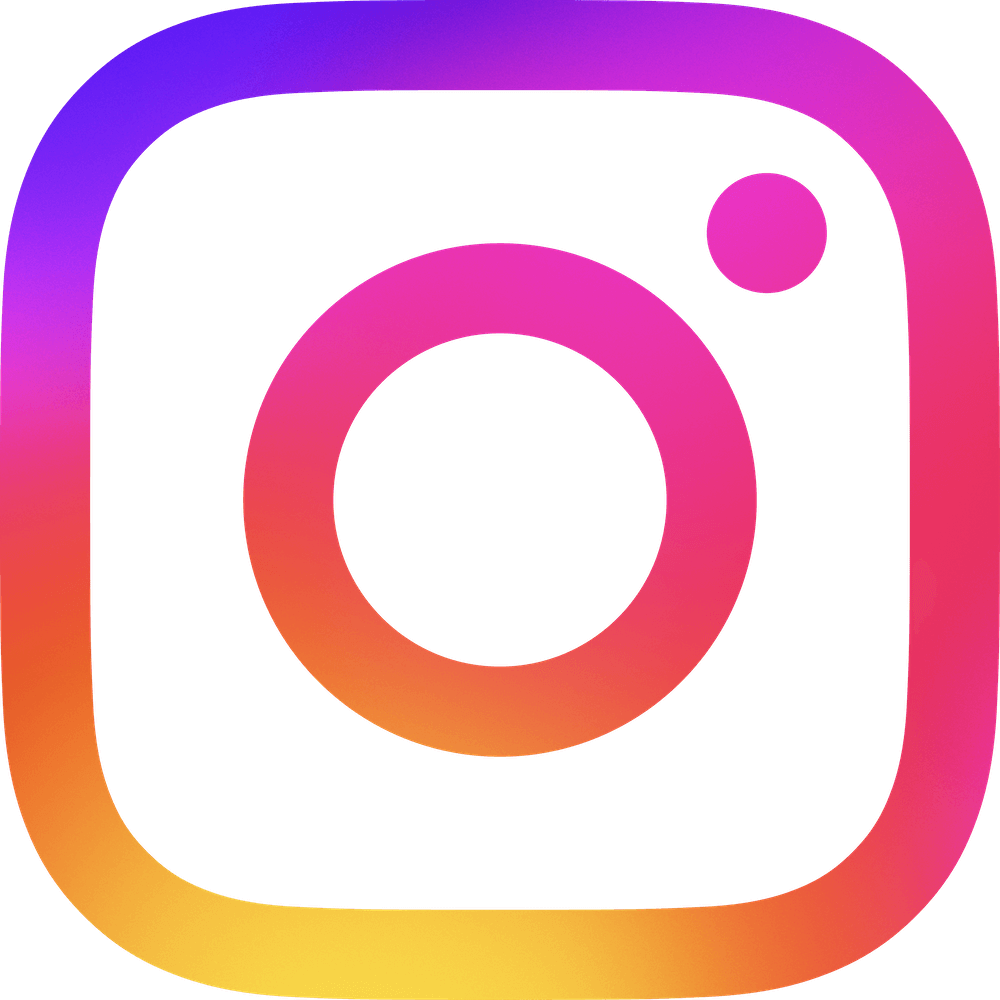
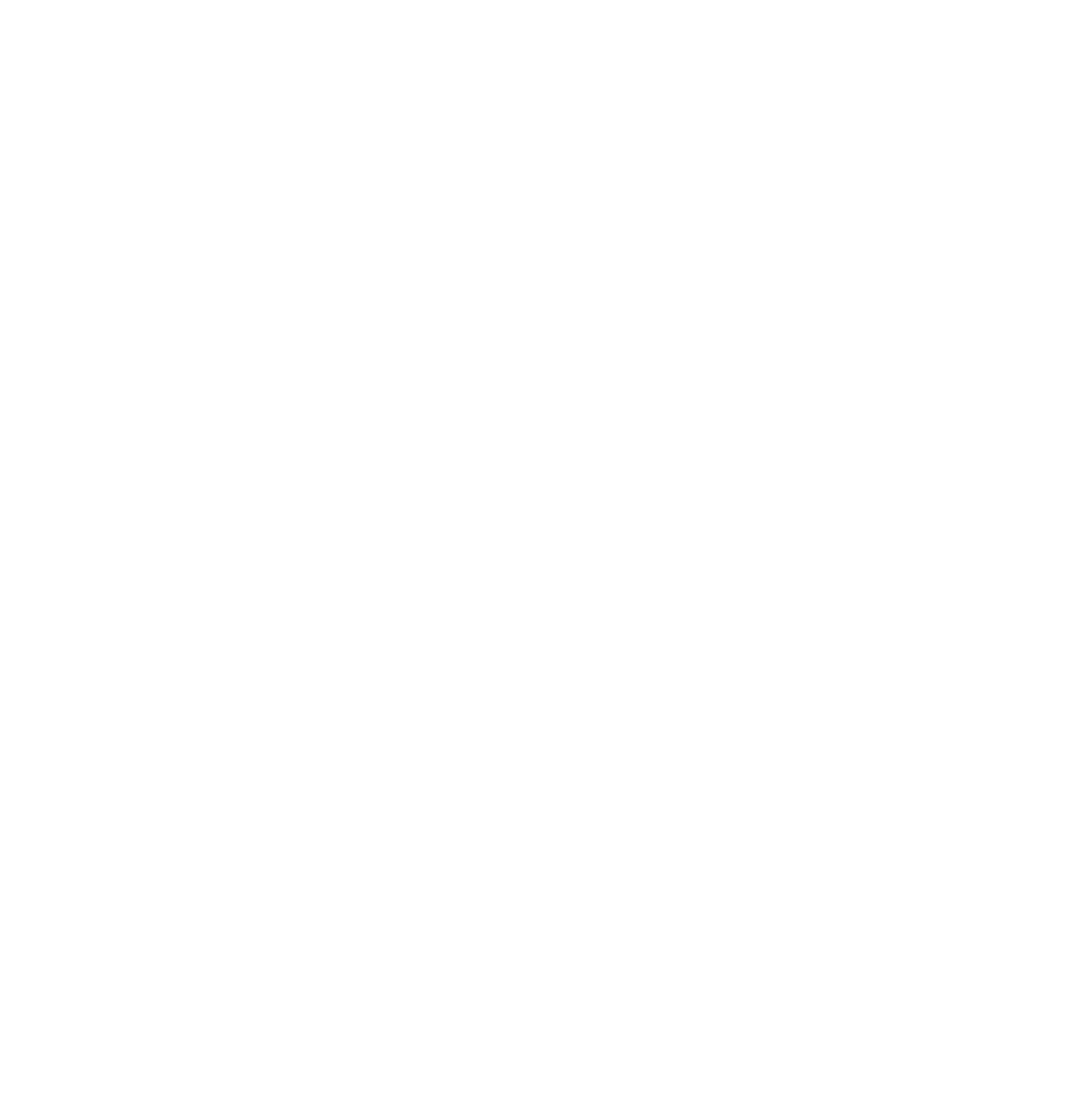


 ベルリンを流れるジュプレー川中州の北半分、5つの博物館・美術館が集まる”博物館島”も、
ベルリンを流れるジュプレー川中州の北半分、5つの博物館・美術館が集まる”博物館島”も、 旧東ベルリンの象徴だった無骨な社会主義建築も、
旧東ベルリンの象徴だった無骨な社会主義建築も、 東西融合のシンボルとして有名なホーネッカーとプレジネフのキスを描いた
東西融合のシンボルとして有名なホーネッカーとプレジネフのキスを描いた ドイツが生んだ写真家、故ヘルムート・ニュートンの代表作”Walking Woman”が壁一面に飾られた
ドイツが生んだ写真家、故ヘルムート・ニュートンの代表作”Walking Woman”が壁一面に飾られた 旧東ベルリンの信号機に用いられていたキャラクター”アンペルマン”。
旧東ベルリンの信号機に用いられていたキャラクター”アンペルマン”。