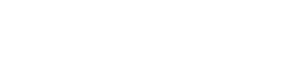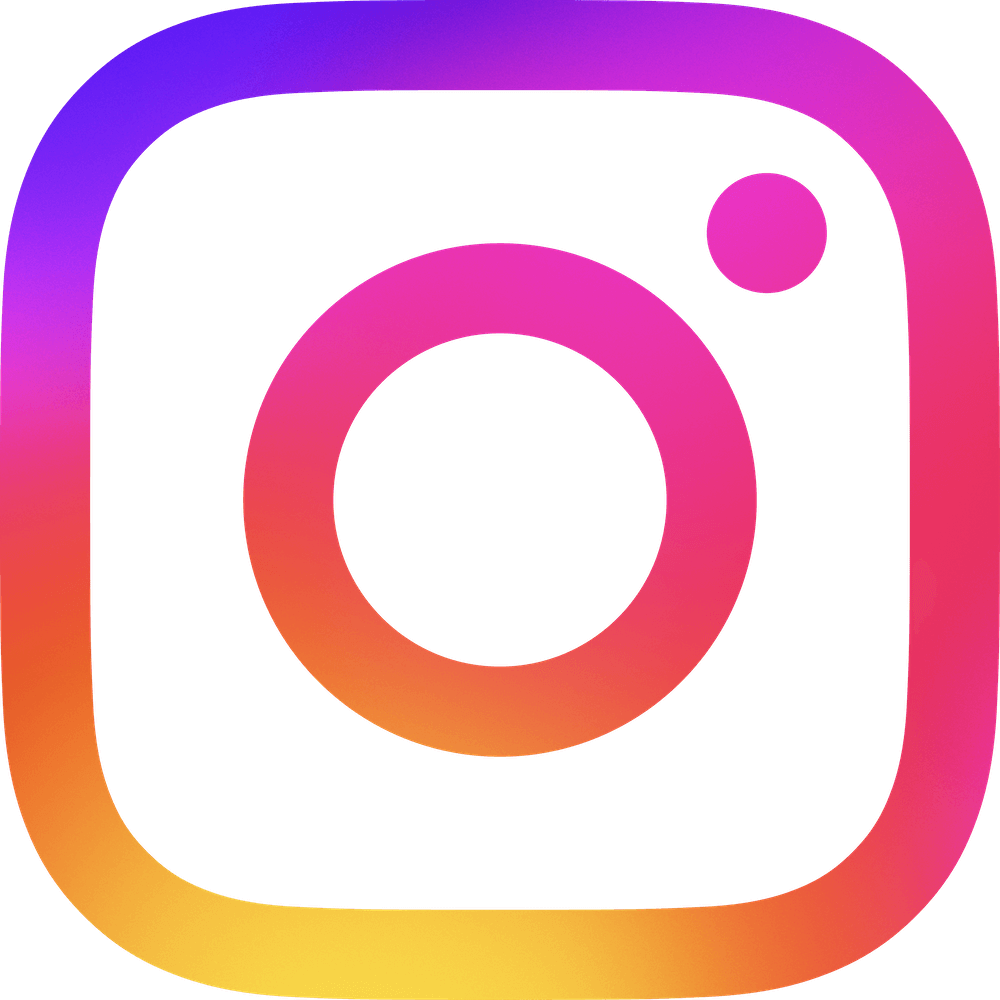オンロードもオフロードもこの1台で。Jeep初の100%電気自動車アベンジャーを体感
【インプレッション】今回はモータージャーナリストの嶋田智之さんに、Jeep初の100%電気自動車・アベンジャーを試乗してもらったインプレッションをお届け!アベンジャーの持つポテンシャルとは?
Jeep初の電気自動車は日本の道路事情との相性抜群
えっ? Jeepが電気自動車? ……Jeepなのに? 2022年に『ジープ アベンジャー(Jeep Avenger)』が発表されたときには、そんなふうに疑問を感じた人も少なくなかったようだ。Jeepの名前にイコールで結ばれる“冒険”というキーワードと、どこかでバッテリーを充電しないと走れない電気自動車のイメージが、上手くリンクしなかったのだろう。
ところが僕はちょっと違って、もしかしたらかなり強力な悪路走破性を持った未来のJeepの姿を、ふと想像してしまった。モーター駆動のクルマに慣れ親しんだ人の多くはそうだと思うのだけど、電気モーターと電子制御の相性が抜群にいいから、人間のペダル操作を遙かに凌ぐ繊細かつ高度な駆動制御が可能になるということを知っている。名人クラスならもしかしたら話は別かもしれないけど、僕たちのような凡百のドライバーががんばってもなかなか到達できない究極的な環境下における微細なアクセルワークやブレーキワークを、クルマの方が自在に調整して実行してくれる、というわけだ。アベンジャーは、それも発表時に披露され“4×4コンセプト”は、そうした可能性をしっかりと示してくれたのだ。
ただ、それは今のところ近未来への展望であって、バッテリーとモーターで走るJeepが持ちうる大きなメリットのひとつに想いを馳せたというだけのお話。バッテリーとモーターで走る電気自動車(以下、BEV)のメリットは、そこだけじゃない。それにJeepというブランドが好きだからと言って、誰もが道なき道ばかりを走りたいというわけでもない。
その点を考えると、Jeepがアベンジャーのスタートを前輪駆動のBEVに任せたことに、素直に頷ける。すでに何度かステアリングを握らせてもらっているのだが、BEVの基本的なメリットをしっかり押さえた上に、道なき道の少し手前ぐらいまでなら足を踏み入れて行けそうな走破性を確保して、Jeepとしてのプライドを保っていることにも感心している。実は個人的に、BEVの中ではかなり気を惹かれているモデルでもある。
▲モータージャーナリストの嶋田智之さん
なぜかというと、まずはそのサイズだ。皆さんもご存知のとおり、アベンジャーはこれまで最もコンパクトだった『ジープ レネゲード(Jeep Renegade)』よりもさらに小さな、BセグメントのSUVとして企画されている。全長4,105mm、全幅1,775mm、全高1,595mmという車体の大きさはインポートSUVとしては最小の部類で、走らせてみると一発でわかるのだけど、この日本という国の道路事情に見事なくらいマッチしている。車体の四隅が掴みやすいスクエア気味のデザインも手助けしてくれるから、混み合った街中や狭い駐車場などでも取り回しに難儀することがない。
Jeepならではの遊び心とデザイン、そして機能美
スタイリングデザインそのものも見事だと思う。デザインの系統としては『ジープ グランドチェロキー(Jeep Grand Cherokee)』のラインと言えるのだろうが、その堂々とした世界観を80cm近くショートで20cmほどタイト、同じく20cmほど低い車体にきっちりと再現している。内燃エンジンが載ってないから塞がれてはいるものの、象徴的な7スロットグリルも含め、どこからどう見てもJeepの存在感。素直にカッコいいな、と思わされる。それに、これは実際にアベンジャーを見ながら発見を楽しんで欲しいから詳細を語るのはヤメにしておくけれど、初代Jeepの顔、てんとう虫、望遠鏡を覗く少年と星空、岩山……などなど、たくさんの隠れキャラがデザインの中に織り込まれていて、そうした遊び心に楽しい気持ちにさせられるのもJeepらしいところだ。
遊び心と言えばウインカーの音もそうで、カッチッカッチッ……という素っ気ない音であるのが普通なのに、アベンジャーはまったく違っている。ズンカッズンカッズンカッ♪ という、ドラムのバスドラとスネアのリムでリズムを取るような、何だかブルージーな雰囲気のサウンドで楽しませてくれるのだ。このクルマの企画に携わった人たち自身が楽しい人たちなんだということが推察できて、嬉しくなる。
インテリアに目を移すと、そこは一点、Jeepならではの機能美が表現された世界だ。基本的な構造は、同じステランティスの別ブランドの姉妹車たちと共通だが、ディテールに手を入れることで、Jeepならではの雰囲気を巧みに作り上げている。これもまた姉妹車たちと共通なのだけど、10.25インチのディプレイの機能にアクセスするためのモノやシフトセレクター、空調系なども含めた物理スイッチのレイアウトも適切で、慣れればブラインド操作が可能だし、センターコンソール下部にあるワイヤレスチャージ用パッドを内包した大型で彫りの深い小物入れなども実に使いやすい。この小物入れ、車内に乗り込んで脱いだ薄手のダウンくらいなら、丸めてポイと放り込めるくらいの容量があるから、アウトドア好きなユーザーには、かなり重宝することだろう。室内の空間も、車体のサイズのわりに窮屈さはなく、大人4人なら楽々過ごせるくらいの広さはある。
オンロードもオフロードも安心して身を任せられるアベンジャーの走行性能
他にもいろいろと美点はあるのだけど、何より僕が気に入ったのは、そして皆さんにお伝えしたいのは、アベンジャーの乗り味そのものだ。日頃は街乗り主体──どんなクルマでも基本はそうなのだけど──というユーザーには、今からでもショールームに行って試乗してみることをオススメしたいくらい上質なのだから。
アベンジャーの基本的な構造は、ほかの姉妹車たちと同じくステランティスのeCMPプラットフォームの上に成り立っている。最大の重量物であるバッテリーをフロアに敷き、フロントに電気モーターやコントローラーをマウントして前輪を駆動する、というレイアウトだ。これはBEV全体に関して言えることなのだけど、そうした走るためのメカニズムをレイアウトする自由度が高く、内燃エンジンのクルマと比べて重心を低く設定でき、さらには内燃エンジンのクルマよりも車重が重いのが常なので、ハンドリングのフィールやコーナリング性能、それに乗り心地の面でだいぶ有利となる。実はバッテリーとモーターで走るクルマの最大のメリットはそこにあって、アベンジャーはそれを最大限に活かして開発されているのだ。
走り始めると、まずは先述のサイズ感にホッとした気持ちになる。とりわけ都市部でクルマを走らせるときには、小ささというのは圧倒的な正義だとすら感じられる。その次にニンマリとできるのは、乗り心地の良さだ。柔らかいというより、どちらかといえば引き締まったフィールではあるのだけど、路面の凹凸やざらつき、うねりなどの外乱を、大小に関わらずしっかり吸収してくれるのだ。高めの速度でバンプを乗り越えるようなときでも、嫌な突き上げ感や底付き感はない。速度域が高くなっていくと、さらにしなやかさを増して、フラットな印象に。車体のしっかり感、サスペンションの動き、タイヤの性格などが高いレベルでバランスを保っていないと、こうはならない。
そして、Jeepにしては異例と言ってしまいたいくらいの、オンロードにおけるスポーティなハンドリングだ。スポーツカーのようにシャープと言うつもりはないけれど、ステアリング操作に対して遅れなく素直にノーズが向きを変え、適切なロールを感じさせながら、綺麗なオン・ザ・レールの正確なターンを決めてくれる。シャーシの動きに上屋がついてこられずに揺さぶられるようなことは微塵もなく、コーナー続きの道でも素晴らしくリズミカルに、実に気持ちよく駆け抜けることができるわけだ。現時点において、Jeep史上で最もオンロードでのハンドリングとコーナリングに優れたモデル、と断言してもバチは当たらないだろう。
肝心のパワートレイン(エンジンで発生した回転エネルギーを駆動輪に効率よく伝達する装置群の総称)に関しても触れておかないとならない。最高出力156ps、最大トルク270Nmのモーター性能や54kWhというリチウムイオン電池の総電力量は、これまた姉妹車たちと共通。その数値を見ると、もしかしたら心許なさを感じてしまう人もいるかもしれない。けれど、ご心配なく。モーター特有のアクセルペダルを踏んだ瞬間に持てるチカラのすべてを発揮できる特性は、もちろんこのクルマにもあてはまる。なので、発進から高速域まで力強く一気に、俊敏ともいえる加速を披露してくれる。高速道路の制限速度くらいまでしか試すことはできてないが、その領域ぐらいまでなら全くトルクの落ち込みもないし、得られるスピードにもまったく不満はない。過剰さはないが、結構なパフォーマンスなのだ。
そして特筆すべきは制御の巧みさで、いかにもBEVだといわんばかりの瞬時にトルクを膨らませるわざとらしい仕立てではなく、穏やかに発進してペダルの踏み込み加減に合わせてスムーズに力強さを増していくような大人な味つけとされていることだ。シフトセレクターのDボタンをもう一度プッシュしてBモードに入れると回生ブレーキ(ハイブリッド車や電気自動車などで使用されるブレーキシステム)の強さが高まるし、走行モードをスポーツに切り換えれば加速の強力さも増すのだが、その減速G、加速Gにも尖った感じはなく、とても扱いやすい。BEVだということも必要以上に意識させられることがない。そうした自然なフィーリングが、このクルマの心地好さに繋がっている。
と、ここまでご覧になって、要は街乗り用のBEVとしては出来がいいわけだね、なんてクールな見方をする方もおられるかもしれない。まぁ、たしかに街乗り用のBEV、街乗り用のSUVとしては抜群と表現したくなるくらいの出来映えだ。そこを否定する気は一切ない。
電気自動車も“冒険”を大切にしてきたJeepであるべき理由
けれど、それだけでもない。今回改めて感じたのは、やっぱりJeepは自分たちがなすべきことをやっているのだな、ということ。ちょっとしたオフロードコースにアベンジャーで侵入してみて、ここでも思わずニンマリしちゃったのだ。
アベンジャーには、前輪駆動のJeepとしては初めて、「ノーマル」「エコ」「スポーツ」「スノー」「マッド」「サンド」という6つの走行モードを切り換えられるセレクテレインシステムと、ヒルディセントコントールが与えられている。最低地上高は200mm、アプローチアングルは20度、デパーチャーアングルは32度。この数字が意味するものが何かは、Jeep好きなら言わずとも理解されていることだろう。そこそこの悪路ならクリアできるように考えられている、ということだ。
コースでは主としてスノー、マッド、サンドの3つを切り換えながら走ってみた。ここは週末になると『ジープ ラングラー(Jeep Wrangler)』のような超本格派が強力な走破性を楽しむために走るようなところでもある。もちろんラングラー並みだなんて考えているわけじゃないし、履いているのはノーマルタイヤだし、何より自分がオフロードの素人であることを心得ているから、事前に自分の足でチェックしてからアベンジャーを進入させたわけだが、ちょっとした小川のような流れも、砂利と玉石が浮いている坂の登り降りも、自分の足では入っていきたくないぬかるみも、相当に注意深くステアリングを操作したりペダルを操作したりすることが必要だった場面はあったけど、しっかりクリアできてしまったのだ。これは嬉しい驚きだった。
3つのモードではそれぞれ加減は異なるものの、ドライバーのアクセルペダルの踏み込み具合いに対して慎重に路面を掴むような静かな駆動を地面に伝える制御をしてくれるから、ズルリとタイヤを空転させてしまうことがほとんどなかった。あったとしても、もとよりこちらは空転前提で慎重にペダル操作をしていることもあって、その動きが緩やかなものとして感じられるから、瞬時に踏み込み量を調整できて、クルマをジワッと前に進んだり後退したりすることができた。
当然ながら地面の状況はケース・バイ・ケースだし、ドライバーの注意深さやペダル操作の繊細さなどによっても大きく変わるし、だから絶対に大丈夫だなんて申し上げるつもりはないのだけど、個人的には予想と期待を軽く上回る走破性を見せてもらえたな、と感じている。これがモーターと電子制御の合わせ技。FWDであっても結構やるヤツなんだな、と感心すらしている。これくらいのパフォーマンスがあれば、週末のキャンプでアウトドアでの遊びで、それまでのクルマよりもう少し深い冒険を楽しむこともできそうだ。
電気自動車の可能性と次の一手となるアベンジャーの存在
ちなみにBEVとしての航続距離に関して触れておくと、カタログ値ではWLTCモードで486km。もちろん走行環境や状況によって航続距離は変化するものだし、さすがにバッテリー残量ゼロ近くまで持っていく勇気もないのだけど、これまで何度かクルマをお借りして走行と充電を繰り返してきた感覚からいうと、満充電で普通に350km以上はマークしてきていて、おそらく380km近くまではマークできそうな感じだった。BEVの平均電費が電力量1kWhあたり6kmといわれているが、区間によっては8kmを越えたこともあったから、電費は良好な方なんだろうと思う。
30分の急速充電は、やってみれば意外と苦にならない……というかスマートフォンでSNSを見たりメールの返信をしていたりするとすぐに過ぎちゃうし、高速道路のサービスエリアでは食事できるほどの時間でもないくらい。住環境にもよるけれど、急速充電器もだいぶ数が増えてきて、充電スポットを教えてくれるアプリもかなり有効だから、外出先での充電に困ることもほとんどなくなってきた実感がある。
そんなこんなで、本格的なラフロードに走りに行く気はないけど、たまに気持ちのいいバーベキューの場所を探すためにちょっと深い場所まで行ってみたいという僕にとって、アベンジャーは最も欲しいBEVランキングの最上位に近いところに位置するモデルとなったのだった。
アベンジャーに関連する他記事はこちら!
カタログ請求はこちら!
ご試乗予約はこちら!
商品に関するお問い合わせは、Stellantisジャパン株式会社まで。
ジープ フリーコール 0120-712-812(9:00~21:00、無休)
https://www.jeep-japan.com/
【クレジット】
Text:嶋田 智之
Photos:大石 隼土